#5 「BUYMA」成長ストーリーから学ぶ、新規事業立ち上げに必要な考え エニグモ代表・須田 将啓氏
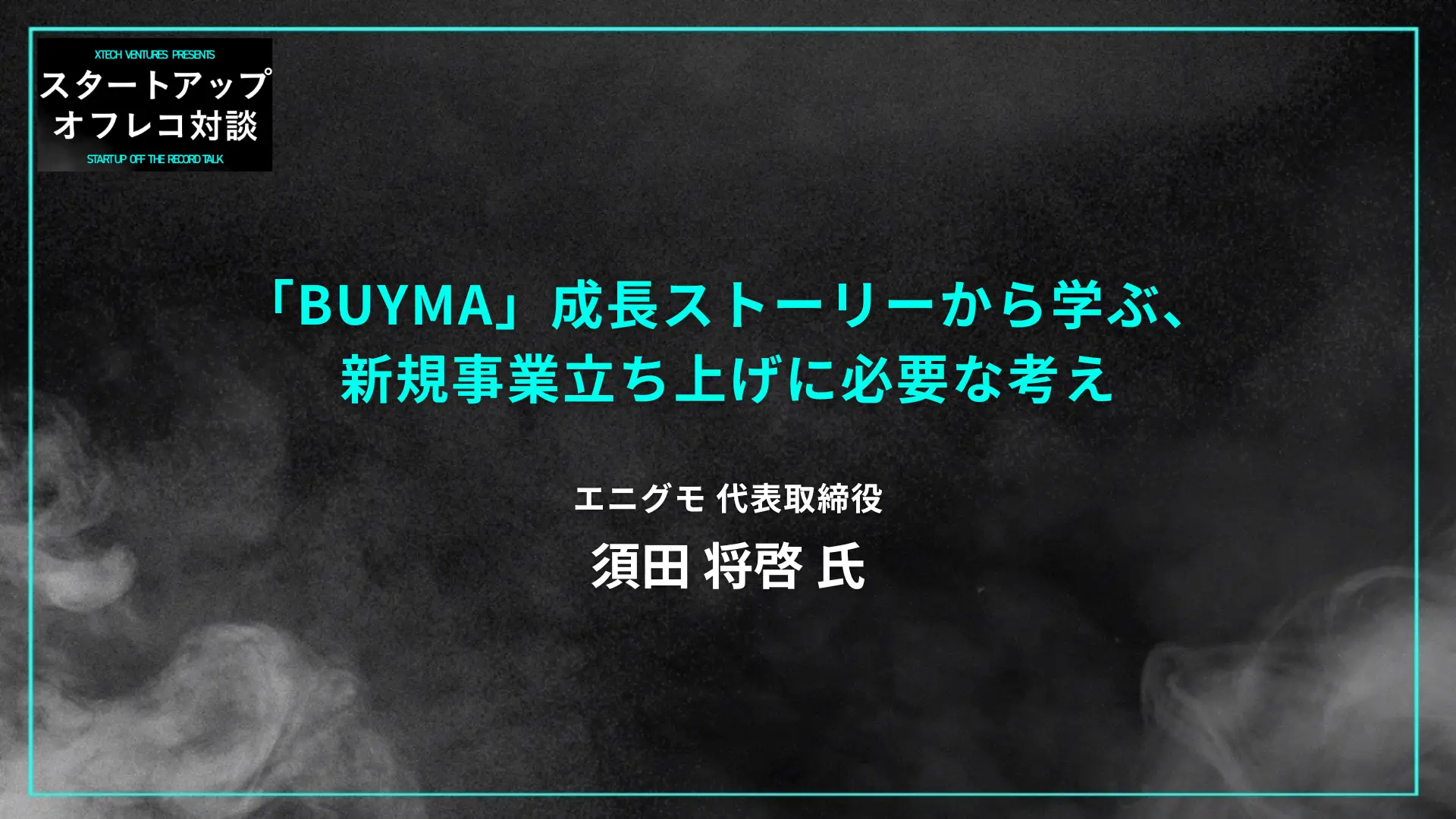
#5 「BUYMA」成長ストーリーから学ぶ、新規事業立ち上げに必要な考え エニグモ代表・須田 将啓氏
📕Summary
「スタートアップ オフレコ対談」は、XTech Venturesの代表手嶋とゲストの方をお呼びして対談する番組です。今回はエニグモ代表の須田さんをゲストに迎え、C2Cマーケットプレイス「BUYMA」について伺いました。
ネットで物を買うことも怪しまれた当時、様々な壁にぶつかりながら、どのようにして難易度の高い、全く新しいビジネスモデルを立ち上げたのか。前半では、様々な壁にぶつかりながら、難易度の高い新しいビジネスモデルを立ち上げた創業ストーリーを振り返ります。
🔊Speaker
・手嶋 浩己(@tessy11)
XTech Ventures代表パートナー
対談内容
※記事の内容は2021年11月時点のものです。
「BUYMA」立ち上げ当時の時代背景
手嶋:私と須田さんは博報堂の新卒同期で、もう20年ぐらいのお付き合いになります。須田さん、さらっと自己紹介をお願いできますか。
須田:茨城県水戸市に生まれて、地元でずっと地域活性化プロジェクトをやっていました。大学から東京に出てきて、大学院を卒業後に博報堂に入って、そこで手嶋さんと同じ部署だったんです。部署のメンバーにもう1人、田中という同期がいて、その田中と一緒に創業したのがエニグモです。博報堂にいたのは4年ぐらいですかね。
最初につくったサービスが「BUYMA」でしたが、最初はなかなか立ち上がらなくて。並行して広告事業で短期的な利益を上げつつ、「BUYMA」は投資をして育てていくという2本立てのポートフォリオでやってきました。「BUYMA」が育ってきたタイミングで、リーマンショックの影響もあり、事業を1本に絞ることにしました。そこから業績も安定して伸びてきて、上場して今に至るという感じです。
手嶋:15年を駆け足でわかりやすくご説明いただきました。起業家の人たちは、「BUYMA」のようなC2Cのマーケットプレイス事業を立ち上げるのに憧れてる人も多いと思うんですよね。めちゃくちゃインターネットライクな事業なんで。でも、実現するのがなかなか難しいドメインだと思います。「BUYMA」のサービスインは2005年でしたっけ?
須田:2005年です。
手嶋:当時は、Facebookがアメリカで生まれてるか生まれてないかくらいですかね。日本ではちょうどブログが出てきて、Facebook広告で集客とかも当然できませんという時代。Googleのリスティング広告やYahoo!ディスプレイアドネットワーク(当時)くらいですかね。なので、今と「BUYMA」の立ち上げた時では全く環境が違うと思うんですが、いくつか具体的に教えてもらってもいいですか?
須田:ヒト・モノ・カネ、全ての状況が今とはかなり違いますね。まず、エンジニアも、eコマースをやっている人材もほとんどいない。サービスの立ち上げについて、誰かに聞いて経験をシェアしてもらうみたいなショートカットはまずできませんでした。
あと、そもそもプログラム自体が今のように簡単ではなく、フレームワークもクラウドサービスも全く無いし、サーバー1個500万円みたいな世界だったので。最初にやり始めるハードルがとにかく高かったというのが1つ目の違いです。
2つ目はやっぱり資金面。今だと10億円単位の資金調達も少なくありませんが、当時は1億円でもなかなか集めにくかった。ユーザーの心理面でも、eコマースで物を買うこと自体がまだそこまで広まっていなかったんです。当時は「クレジットカードをネットに登録するのも怖い」とか、「知らない人から物を買うのが不安」という声が多く、買う側のハードルが高かったなと思います。
手嶋:正直、よく立ち上がったなと思いました。「奇跡のサービス」だという面もあるのではないですかね。エニグモって、未上場のときの累計資金調達額はいくらぐらいだったんですか?
須田:累計で9億円ぐらいですね。
手嶋:それでもかなり調達できたほうだよね、当時からすると。9億円を調達して、かつ広告事業でも数億円ぐらいの利益が出ていて、それを「BUYMA」に突っ込んだという感じ?
須田:そうですね、累計で10億円以上は突っ込んでましたね。
手嶋:なるほど。2012年に上場したときは、もう数億の利益が出てたもんね。
須田:上場した年で、多分2億円ぐらいは利益が出ていたと思います。
手嶋:2005年にサービスインしてから2012年まで、黒字化するのに7年ぐらい。
須田:通期黒字で、「BUYMA」単体で5年間ぐらいですかね。
C2Cビジネス成功のターニングポイントと反省点
手嶋:僕は須田さんに「実際のところ、なんで立ち上がったの?」って多分20回ぐらい聞いてるのに、いつも「じわじわとだよ」としか答えてくれないんですが(笑)。実際、しっかり長期的に投資しながら本質的に価値あることを諦めずにやり続けた結果だとは思うんですよね。今だから言えることも含めて、小さくてもいいんで、ターニングポイントになった出来事をいくつか教えてほしいです。
須田:本当に手嶋さんが言ってくれたように、じわじわと本質的なことをやり続けたっていうことなんですよ。あえてターニングポイントを挙げていくと、1つ目は、メルカリのように何でも扱うマーケットプレイスを目指していたところから、当時流行していたアバクロのTシャツにフォーカスをしたのが始まりでした。
今だと「BUYMA」で1000万円以上のバッグが売れたりするものの、当時はネットで買うのも怖いという中で、買ってもらえるものはすごく限られていて。それでも売れるのがアバクロでした。数千円で手ごろだけど当時の日本ではほとんど買えないという希少性があったんです。リスクがあっても数千円程度ということで、「買ってみようか」という気にさせる商材がアバクロだった。
最初はユーザーにおまかせで出品してもらったのを、「なるべくアバクロを出品してください」とお願いして商品を集めて。そこで、赤字覚悟で「アバクロ」のキーワードで検索広告を打ったところ、アバクロの商品を探しているユーザーとのマッチングを作り出せた。そうすると、「アバクロを出品すれば売れるんだ」と商品がどんどん増えていって、買う側もアバクロの商品が充実したサイトだと認知して来てくれるようになって。
商品が増えることでSEOもどんどん上がっていって、リスティングに頼らずにアバクロの商品が売れる好循環になっていったんです。その後、他の西海岸系のカジュアルブランドのアパレルが充実していったっていうのが最初のターニングポイントです。
手嶋:今だとCPAやLTVなどの指標も重要視すると思います。リスティング広告でアバクロ目当てで来た人は、アバクロの商品を買ってくれても定着してくれるか全くわからないじゃないですか。その動きは見てたんですか?
須田:当時はあまりそういったユニットエコノミクスの概念がなかったと思うんですよね。メルマガ、雑誌の広告やアフィリエイト広告などもさんざんやってきたけど全くペイしなかった中で、リスティング広告が一番リピート率が高かったんです。
2年半で広告費用が回収できるという分析も出たので、そこからは全部リスティングに寄せる戦略に変えました。2年半かけないと回収できる算段も全くないけど、もうその当時はリスティング広告に全張りするっていう方法で。
手嶋:そこはたしかにターニングポイントというか、思い切る強さってやっぱりあるよね。アバクロが売れてるなというときに、成功するかわからないけど1回突っ込んでみようっていう。計算して回収に2年半かかるとわかった瞬間に「な、長い……」と、腰が引けてしまう人もいるじゃないですか。当時そこまで思い切ることができたのは、他の事業で利益が出たというのもある?
須田:実は、そのときはまだ広告事業のサービスを始めていなくて。なぜ踏み切れたかというと、ちょうどそのときSo-net(ソニー)から6億円調達できたからです。
手嶋:当時すごいニュースになったもんね。
須田:当時で6億円の調達はなかなかありませんでしたからね。一応、年間1億円単位で広告を打つ計画で調達をしていたので、もう3億円は「BUYMA」のリスティングに充てようと決めてました。
手嶋:なるほど。広告予算を決めた上で、「相対的にこれがいいはずだ」という感じの意思決定だったんだね。
須田:うん、もう他に選択肢がないというか。ユニットエコノミクスの観点でいくと、「BUYMA」の場合は出品した商品が売れないとユーザーがどんどん離脱してしまうので、成功体験を感じ続けてもらうためにある程度お金を使ってでもつなぎ留めないといけない。
そのため広告は多めに張っていきました。ただ、1年間やってみると、キーワードをずらっと見てもそのうちの上位2割程度しかコンバージョンしてない。そこを思いっきりカットしたら、広告費は1000万円から200〜300万円まで2割くらい下がって。良い判断ができて、それもある種のターニングポイントでした。
結局、やってみないとわからないことが当時は山ほどあったので。1回全部やってみて、しばらく経ってから検証して絞っていくのが私たちのこれまでの成功パターンかなと思います。
手嶋:なるほど。そういうプラスのターニングポイントもあると思うんですけど、15年間事業を行っている中で、「出遅れたな」とか、「もっと早くやっておけば機会損失しなかったのに」みたいな失敗談ってあるんですか?
たとえば、僕から見るとスマホアプリを出したのはやや遅かったのかなという印象があって。あれはあのタイミングでよかったなっていう感じですか?
須田:そうですね。そんなに遅れたって感じはありませんでした。当時はSEOによる集客力を入れていて効果も出ていたので。アプリはSEOと相性が良くないという点もあり、それほどマイナスのインパクトがあったとは思ってないです。むしろ、余計な機能を入れすぎたことがマイナスでしたかね。
手嶋:たとえば?
須田:今の若い人は知らないかもしれませんが、当時は「写メール」が流行っていて、ガラケーで写真が送れるのがすごく画期的なことだったんです。
それをどうしても使いたくて、携帯で街中にいてもすぐに出品できる機能を考えたものの、実際に出品すると、1個出品するのに10分くらいかかってしまって、「これは誰も使わないだろう」という機能を作ってしまいました。
手嶋:最初はもっと機能を削って、ぱっと出しちゃったほうがよかったってことですね。
須田:完全にその通りで、その機能を実装するのにおそらく1年ぐらいロスしてしまった気がします。
手嶋:結構、作り込み期間が長かったもんね。
須田:社内にエンジニアもいなかったので、外部にアウトソースしていたんです。どんどん機能をあれもこれもつけてくれと依頼していたら、結局その会社が作れなくなってしまって、夜逃げみたいな形でいなくなってしまったこともあって。0から作り直すことになったので、その分、余計に時間もかかったと。
手嶋:今の話は、須田さんの著書(『謎の会社、世界を変える。―エニグモの挑戦』)を読んでいただくと詳しく載ってますのでぜひ読んでみてください(笑)。
営利30億円からの伸びしろ、BUYMA海外事業の手応え
手嶋:「BUYMA」自体は、昨年度で営業利益30億円を超えたんでしたっけ?
須田:はい。
手嶋:上場したときに、中期的に30億円〜50億円の営業利益を目指していて。時期はずれつつも、想定していたスケールに徐々に近づいてきたのが今なのかなと。たとえば、10年後にどのぐらいのサイズになっているか、ここからさらに成長が加速していきそうなのか、今後の伸びしろについて、現場感のニュアンスでいくとどうでしょうか?
須田:日本の「BUYMA」の伸びしろは、TAMでいくと3000億円。ファッション分野でGMVが3000億円はあると考えています。あと10年ぐらいでそこにたどり着くように成長したいと思ってます
手嶋:今は、いわゆるファッションECのどこら辺の需要を取り込んでるんですか? さまざまなファッションECがありますけど。
須田:大きく2つ。1つ目は百貨店など大手のラグジュアリー系ですね。もう1つは、反対にすごくカジュアルで、かつ安くて人とあまりかぶらない1万円程度のファッションブランドです。二極化しているなと思います。
手嶋:なるほど、低単価ラインもあるんだね。
須田:低単価ラインは実はすごく充実していて。低単価のアパレルを「BUYMA」で購入してくれる方のリピート率は高いんです。
手嶋:ファッション以外だと?
須田:今はライフスタイル関連の商品がすごく伸びています。家にいる時間も長いので、家具や雑貨、インテリアは伸びてますね。あとゴルフなどのスポーツ用品やランタンなどの本格的なアウトドア用品も売れています。
手嶋:こだわりの商品を買いたい人が多いのかな。
須田:こだわりも持っているし、あとは日本で買うより安いというのも当然ある。そこまで大きくないマーケットの商品は、日本で在庫を抱えて売るにはどうしても割高になってしまうけど、競争がそこまで激しくないので、多少高くても売れるんです。その中で、本国から買うよりも価格差があって品ぞろえも差があるので、そういった商材はすごく「BUYMA」に合ってるのかもしれません。
手嶋:エニグモ社は、創業時から「世界に向けてビジネスをやりたい」と言ってましたよね。あの手この手でグローバル事業をやってきたと思いますが、US向けの「BUYMA」もいよいよ立ち上がってきましたか?
須田:そうですね。この1年半とかで体制を変えて、まだ規模は小さいんだけども、成長率や戦略、現在のメンバー体制などが、アメリカの市場にすごくフィットしてきたなっていう手応えを感じています。
手嶋:今はまだそんなに強く海外での成功をアピールしていないし、業界の人もそんなに知らないよね。僕はエニグモマニアだから、ずっとIR資料見てるからわかるけど(笑)。
体制を変更して伸びるっていうのは、ピンとこない人が多いんじゃないかなと思っていて。なかなかうまくいかなかったものが、US向けに体制を変えたらうまくいき始めたというのは、具体的に何を変えたんですか?
須田:全部変えたと言うのが正しいかもしれない。今までは韓国・香港・中国本土などアジア向けにやっていたものを、全てUS向けにシフトして、アメリカでビジネスやってたメンバーを入れるようにして。
商材も、一旦バイマの商品を全てUSにも出品して、その中で反応がいいものを絞っていった結果、ラグジュアリー系が反応がいいということで、ラグジュアリーに強いサイトとしてブランディングを変更した。商品単価が非常に高いので、ある程度CPA単価が高くてもペイするんです。比率を守りながら投資も最適化していった感じです。
手嶋:IR資料でも、2019年10月北米を包括した新体制が発足と書いてあったんだけど、北米こそ難しいじゃない、普通だったら。どうして北米にフォーカスしようと思ったんですか?
須田:社内のメンバーの土地勘にしても、普通に考えるとそのままアジアを狙ったほうが正しかったと思うものの、結論としてアジアはあまりうまくいかなかった。やってみて、構造的にも難しいところがわかってきて。ただ、やっぱり「海外戦略を諦めるわけにはいかない」という思いが強かったんです。中国、特に香港でやってたときに、アメリカのアジア人が結構買ってくれていて。アメリカ在住のアジア人は3割ぐらいいるので、それなりに市場はあるんじゃないかと、仮説のもとにやってみた感じですかね。
手嶋:なるほど。今って拠点は日本だけ?
須田:LAにあります。隠れ拠点が。
手嶋:あまり積極的にはPRしてない事実ってことですね。
須田:そうですね。拠点というか、LAのヘッドクォーターみたいな役割の人がいるだけなので。日本とも連絡を取りつつ、事業の判断をしてもらってます。
手嶋:やっぱり、海外進出をする上で拠点はないとダメ?
須田:現地のエージェンシーとやりとりしたり、カスタマーサービスを立ち上げたりもするので、向こうに人がいたほうがやっぱやりやすいなとは思います。あとはやっぱり、コロナ禍の状況も日本と全く違うので。今はまたマスクをしないといけませんが、それ以前にLAのビバリーヒルズに行くと、ブティックの前にものすごい長い行列があったり。あと、日本でいう給付金のような手当が、LAだと今年の9月まで支給されるとか。
その辺の肌感覚ってやっぱり現地にいないとわからないので。誰かしらいないと、施策もちょっと的が外れるなっていうのはありますね。
手嶋:なるほど。今は、グローバル「BUYMA」が新規事業だとしたら、ここに一旦フォーカスしてるって感じ?
須田:そこと、先ほど話に出たライフスタイル商材ですね。
手嶋:US事業は、長期的にはどのくらいの期待値で取り組んでいるんですか? 日本の事業規模を超えるんじゃないかとか含め。
須田:日本と同じぐらいまでは目指してます。市場規模としては日本の7〜8倍あるので。ある程度ユニットエコノミクスが回ってきたら広告は踏んでいけると思います。そうすると、10年後の日本の「BUYMA」とUSグローバル「BUYMA」の規模は同等か、海外のほうが大きいのではないかと思ってます。
手嶋:手応えを感じながら、とはいえユニットエコノミクスに合わせすぎてしまうと、小さい事業で終わってしまうので厳密化せずに成長させていくフェーズかなと思うんですが。ユニットエコノミクスが成立している状態が1だとすると、今どのくらいまで来ていますか?
須田:感覚的に答えると、アメリカは0.5とかですかね。
手嶋:今後、グローバルに事業をやりたい人はやっぱり多いと思います。エニグモも諦めず16年目。ずっと言い続けてあの手この手で、ときには海外出資もしながら、ようやくつかんだチャンスだと思うので、諦めないでやり続けるとなんとかなるかもしれないっていうざっくりとしたまとめですかね、海外事業に関しては。
須田:そうですね。
手嶋:やっぱり、責任者の存在が大きかったんですか?
須田:それはすごく思います。うちの場合はどの事業も、誰がやるかでやっぱり結果が違うので。どこの企業でもそうかもしれませんが。
前半はここまでです。後半はエニグモが立ち上げてきた歴代の新規事業、またエニグモの今後の展望についても伺っていますので是非ご覧ください。
-
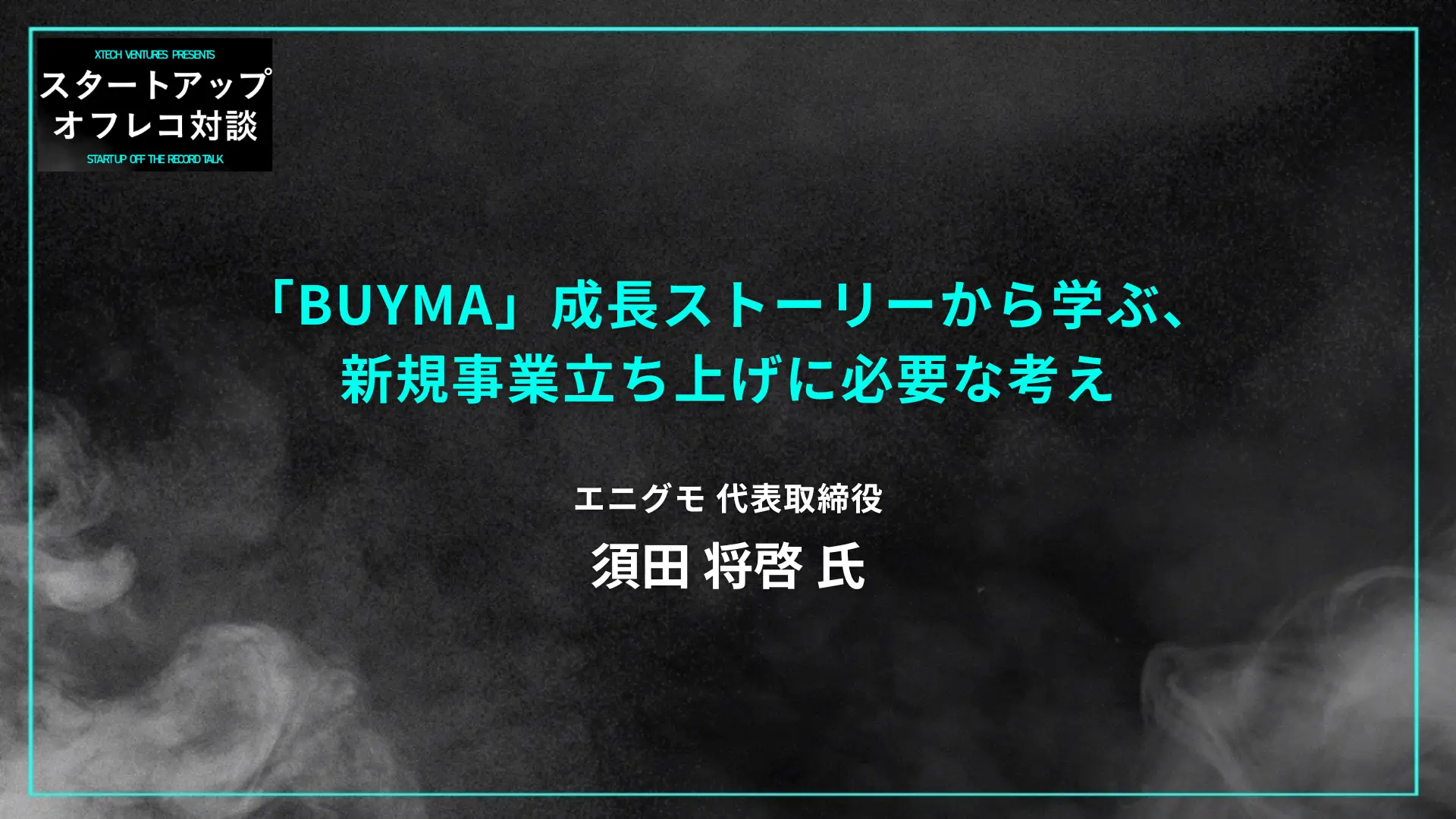 Podcast(書き起こし記事)
Podcast(書き起こし記事)#5 「BUYMA」成長ストーリーから学ぶ、新規事業立ち上げに必要な考え エニグモ代表・須田 将啓氏
-
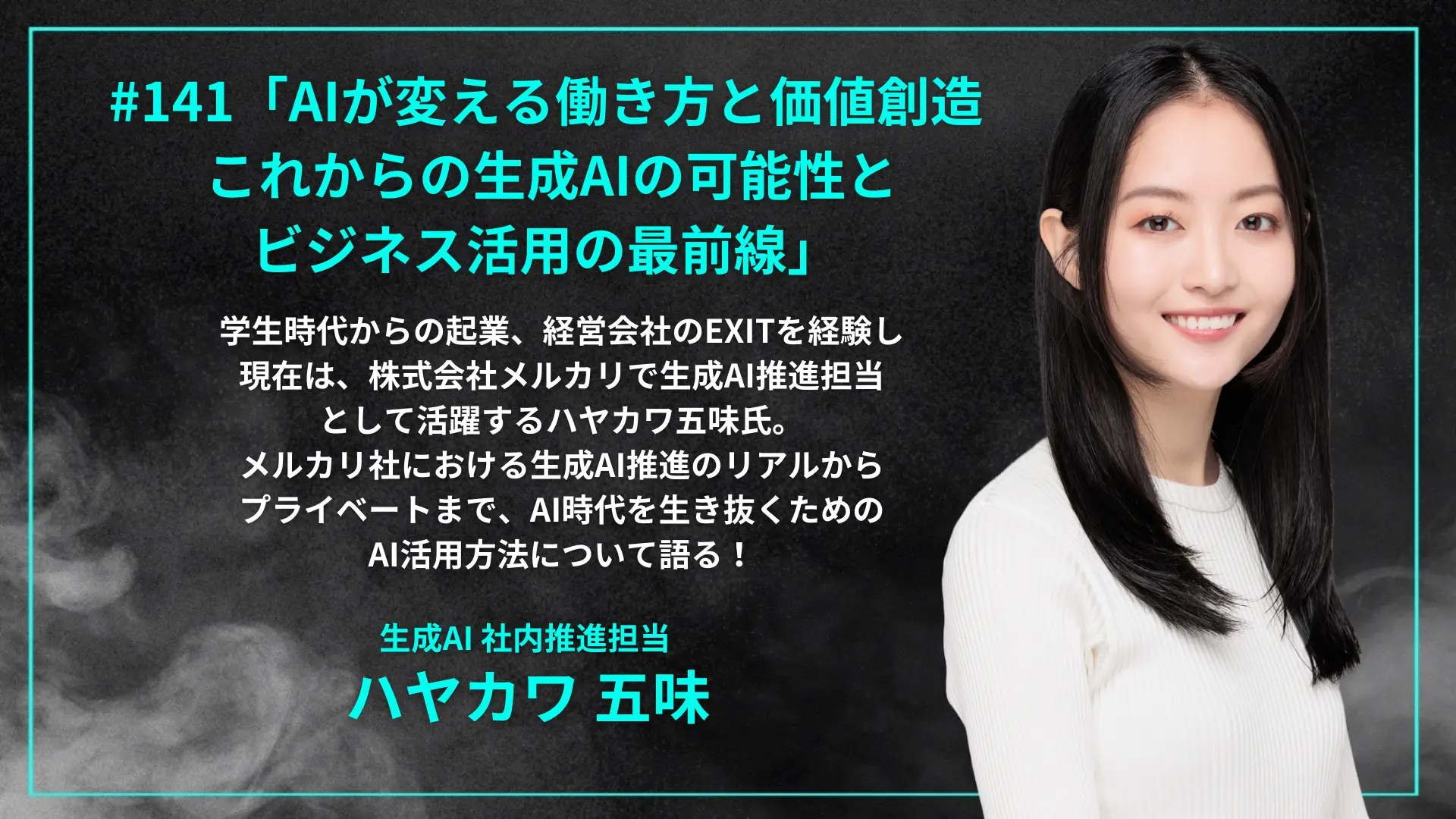 Podcast
Podcast#141「AIが変える働き方と価値創造 - これからの生成AIの可能性とビジネス活用の最前線」 - ハヤカワ...
-
 イベント
イベント東京駅徒歩1分のオフィス利用可!XTech Venturesアクセラプログラム『X-Gate』第7期生の募集...
-
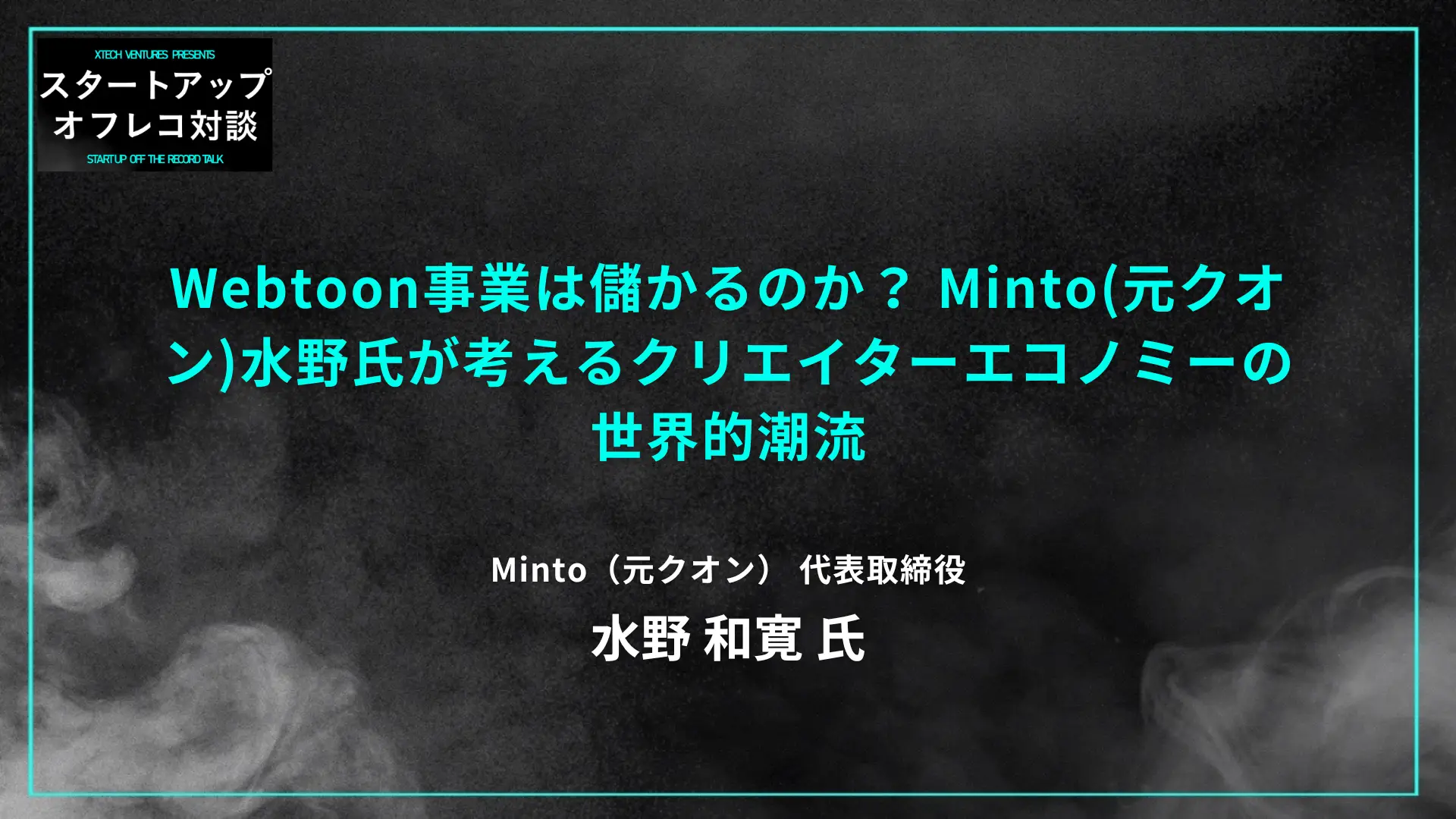 Podcast(書き起こし記事)
Podcast(書き起こし記事)#4 Webtoon事業は儲かるのか? Minto(元クオン)水野氏が考えるクリエイターエコノミーの世界的潮...
-
 登壇情報
登壇情報3月28日に開催される「ごうぎんスタートアップフェス」にXTech Venturesの手嶋が登壇します
