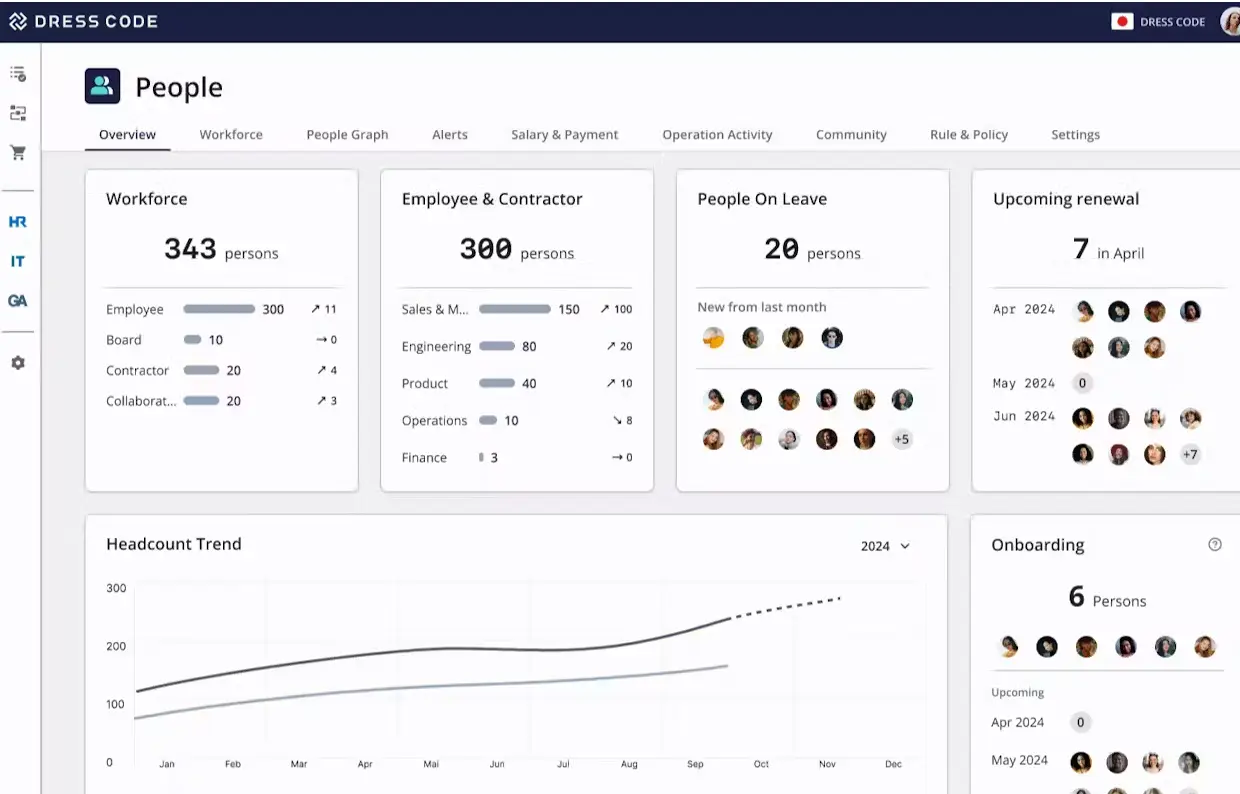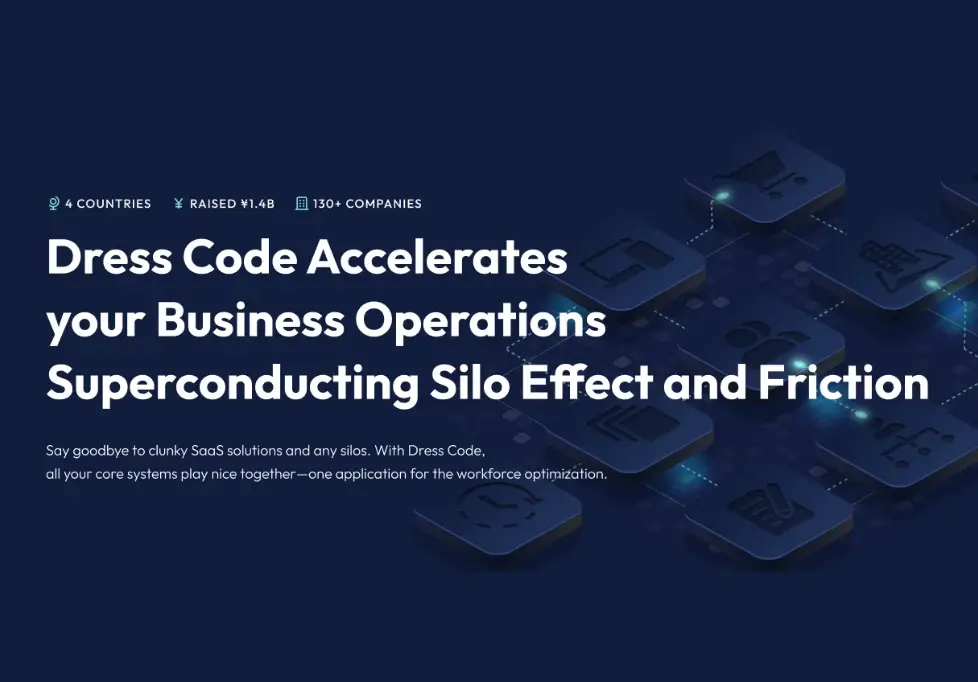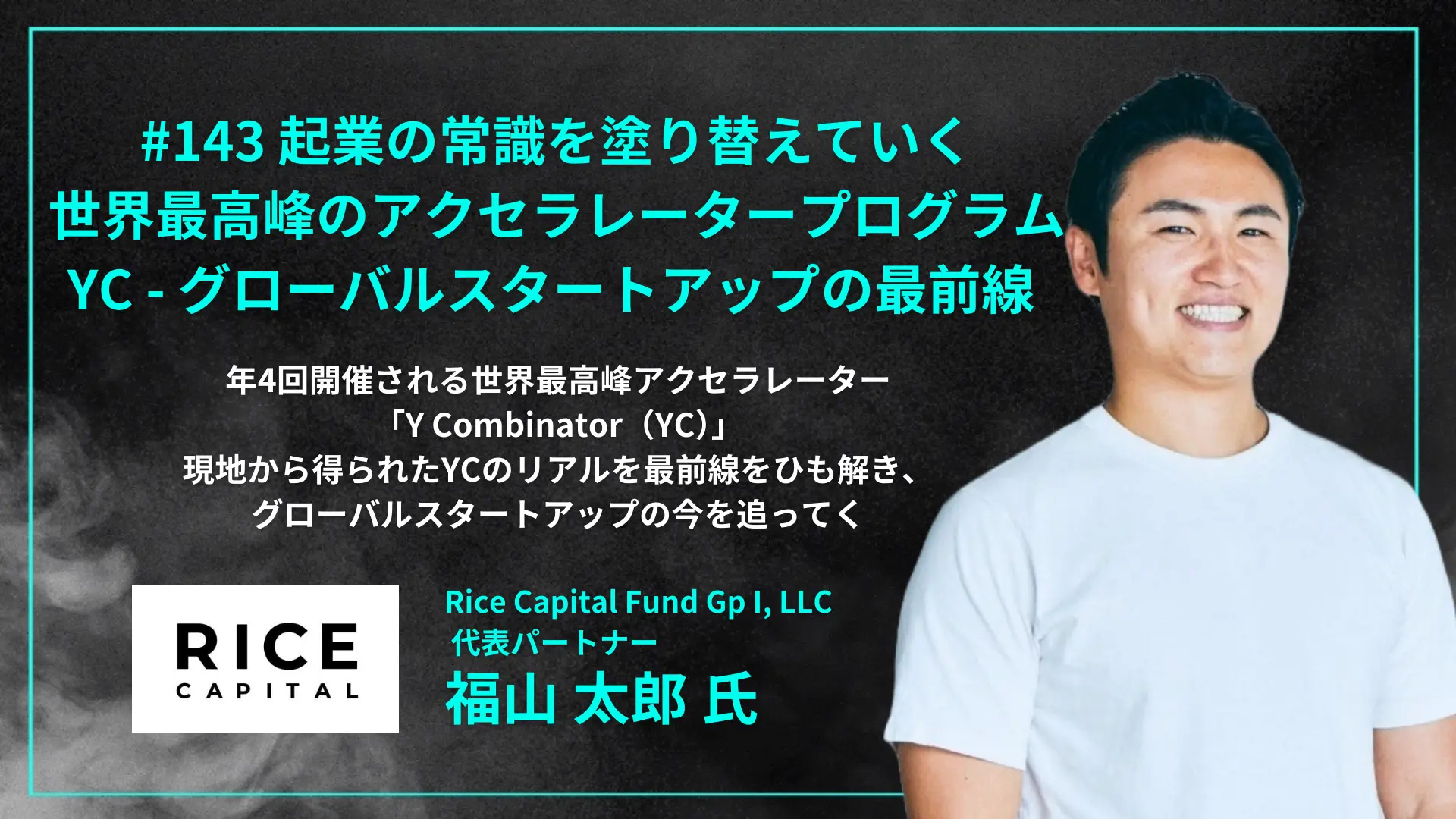#2 メルカリが早期にアメリカ進出を決めた理由。共同創業者に聞く、グローバル展開の舞台裏
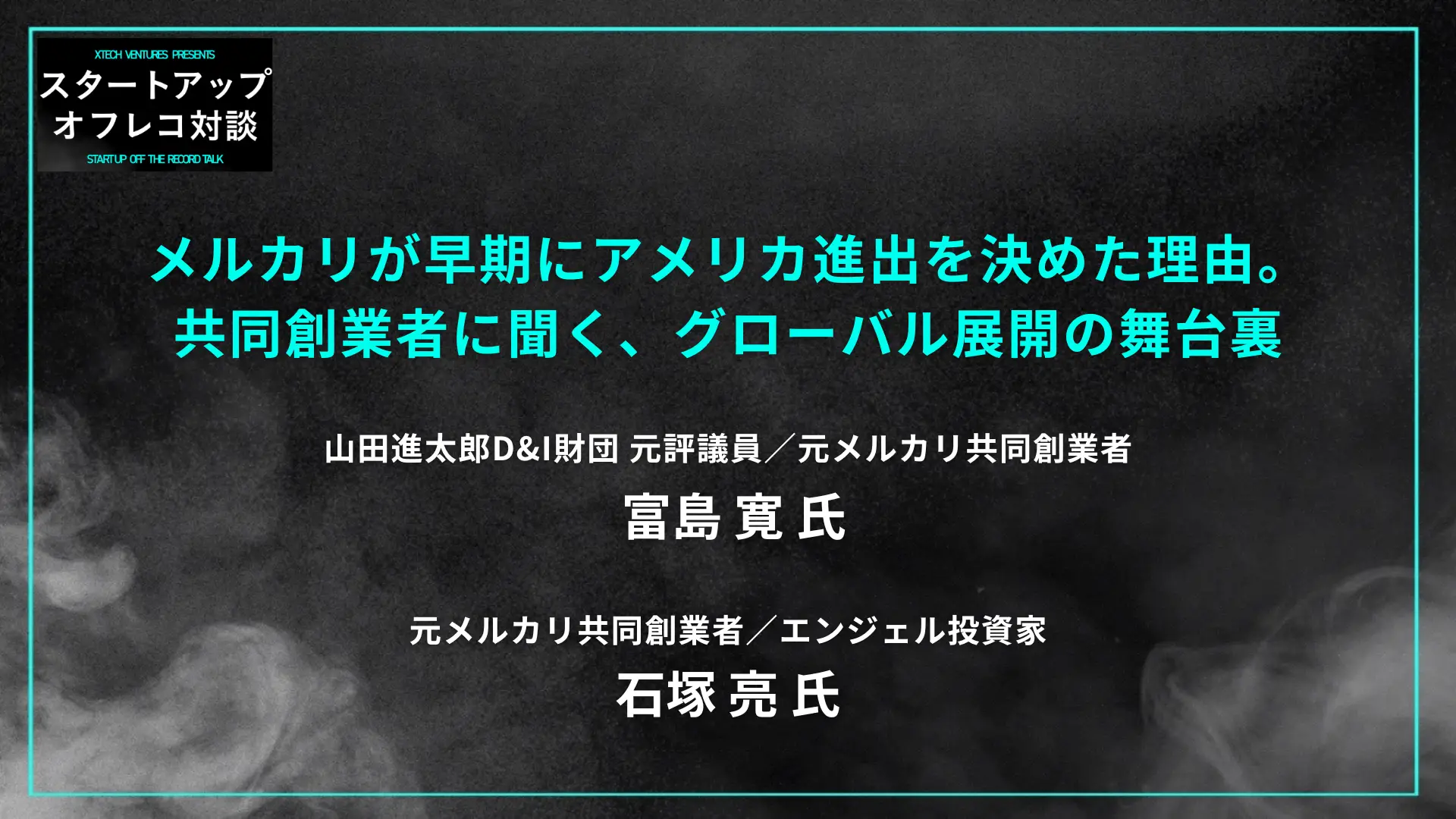
#2 メルカリが早期にアメリカ進出を決めた理由。共同創業者に聞く、グローバル展開の舞台裏
📕Summary
「スタートアップ オフレコ対談」は、ベンチャーキャピタルXTech Venturesの代表手嶋とゲストの方をお呼びして対談する番組です。
そんな記念すべき初回のゲストとして、メルカリの共同創業者の富島さん、石塚亮さんにお越しいただき、2話目は日米リソースの振り分け、ソースコードの分離、退任後の生活などをお伺いしています。
🔊Speaker
・手嶋 浩己
Xアカウント [@tessy11]
XTech Ventures 代表パートナー
・富島 寛 氏
Xアカウント [@TommyTomishima]
山田進太郎D&I財団 元評議員/元メルカリ共同創業者
・石塚 亮 氏
Linkedin[https://www.linkedin.com/in/ryonations]
元メルカリ共同創業者/エンジェル投資家
対談内容
※記事の内容は2021年10月時点のものです。
アメリカ進出へのプロセス
手嶋:では後半戦を開始します。前半戦は主に創業期のメルカリについて、共同創業者だからこそ語れる話をいろいろしてもらいました。
最近の決算でもサプライズとしてメルカリUSが黒字化したというのがかなり話題になっていたなと思います。特に亮はアメリカ進出の責任者で、担当役員をやっていたので、そこを聞いていければなという感じです。
僕の記憶でいくと、2013年の夏にユナイテッドとして投資するときも、確かにアメリカはやりますと言っていたけど、まだ進太郎さんとそんな付き合いが深かったわけじゃないから、どれくらいの強度で言っているのか、正直投資家としては俺はわからなかったのね。
さっきちょろっと話しちゃったんだけど、ユナイテッドが3億円投資して、毎月5,000万広告費かけてるって、トミーが死にそうになっている最中に、いきなりもう2人でアメリカ出張してたよね、進太郎さんと。
石塚:そうですね(笑)。
手嶋:俺は正直、え、今なの?と思ったよね。だって日本はまだGMVが月に数千万とか1億とかなのに、今アメリカ視察してどうするの?って。正直、当事者じゃないから、ちょっと引いたところでは思ってたんだけど。
あれも、亮にアメリカでいずれはやるから入ってよと言われてから、どういうふうに具体的にアメリカ進出に向けて進んでいったの?
石塚:日本でどれくらいまでいったらアメリカ行こうとか、そういった話も具体的にはなかったんです。
ただ、あのタイミングで出張に行ったのは、日本のほうが広告で、ユーザーもどんどん入ってきて、ちゃんと回るようになって、けっこういい感じになってきているというところがありました。
あとアメリカでも、Poshmarkだったり、他にもフリマアプリ系のやつがいろいろと出てきていました。まだどこが勝つかとか、どこがすごいグーンと伸びているという状況ではないけど、いつどこがそうなってもおかしくないという状況で、やっぱ早くアメリカ行ったほうがいいんじゃないか、というような話はあったんです。アメリカに進出したほうがいいんじゃないかと。
あと同時にもう1つ、その出張の前後だったか、ちょっと覚えていないんですけど、同じくらいのときに、WhatsAppがFacebookに具体的な金額は忘れましたけど、めちゃめちゃすごいバリュエーションで買収されて。
手嶋:5,000億とかだったかな。
石塚:LINEってそこになれなかったじゃないですか。アメリカの市場を取って、WhatsAppからアメリカ市場を取ることはできなかった。結局LINEは東南アジアでいろいろと広がっていったけど、でもアメリカを取ることはできなかった。
で、もうこの市場もこれで終わりだろうという感じになって。実際アメリカのほうで、すごい強い会社が出てきたら、もうそれでゲーム終了だよねというところがあったので、それが怖かったんです。
なので、LINEみたいにアメリカ以外の国から攻めるよりも、アメリカに行くことで、そのタイミングは今からやったほうがいいというような考えを持ちはじめていていました。
じゃあ、実際にアメリカに行ってうまくいくのかどうか。とりあえずは見て、いろいろとヒアリングしてみようよというような感じで、出張に行ったんです。
手嶋:出張の成果って、そのときの。
石塚:メルカリのアプリを、そのためにあえて英語にローカライズされたやつをつくって、それでいろいろな人に見てもらって、「こういうのをつくったんだよね、どう思う?」というようなこともヒアリングをして、かなり感触が良かったことですね。
あと、実際に現地のアプリを使ってみても、使いやすさとか機能とか、そういったところに関しても別に遜色はないよねというのがわかったので、アメリカ行ってもいけるんじゃないかという確信が得られたということです。
さっきも話したように、行くなら早く行ったほうがいい。そういう理由で、アメリカ進出しようというのを決めました。
手嶋:小泉さんが入ってくるか来ないかくらいのときだと思うんだけど。2人で出張に行って、大枠は出張中に決めたの?
石塚:そこで決めたわけではないですけど、トミーとも話さなきゃいけないですし。ただ、少なくとも自分と進太郎さんの間ではこれ行けるんじゃないの、行ったほうがいいよねという感じにはなっていました。
手嶋:トミーは現地に行ってないわけじゃない、当時。
もう行ったほうがいいって聞いたときは、日本はCSが混乱したりとか、しっちゃかめっちゃかにサーバが落ちたりしている中でもう行ったほうがいいって帰ってきて、なんて言ったの?
富島:あんま覚えてないんですよね、そこらへん。記憶があんまなくて(笑)。
石塚:忙しすぎて(笑)。
富島:今もそうだし、昔もそうだったと思いますけど、日本のインターネット業界の人も、アメリカに対する、より昔憧れが強かった気がしていて。
自分もアメリカ行って、いろいろなイベント参加したりとかもしてて。その前やっていた会社の、バンク・オブ・イノベーションというところでは、最初動画の検索エンジンを出したんですけど、それとかは最初から英語化とかして、英語のお客さんとかも多かったので、海外向けのことをやりたいという気持ちはけっこうずっと蓄積されていて。
だから、まずめちゃめちゃやりたいという気持ちはあったんですよね。現実問題としてどうかというと、さっきみたいな感じで、カスタマーサポートとか、お問い合わせとかがかなりパンクしているような状態でかつ、まだテレビCMも始まっていない、有料化もしていない、みたいな感じの状況でしたよね。
ただ、年明けてから徐々にその準備を始めていったというふうに記憶していますね。だから、実際には3月くらいからたぶん開発は、アメリカ版を始めたんじゃないですかね。
石塚:出張から帰ってきてから、やっぱアメリカ行ったほうがいいよねという話にはなったけど、ただ現実問題として、今日本は大変な状況ですとか、今自分が抱えているタスクとか、マーケティングもまだ攻めていかなきゃいけないし、テレビCMを視野に入れた資金調達もそろそろ始めなきゃいけないという状況で、自分の課題というタスクもあるので、じゃあそれ俺がアメリカ行ったらどうするの?という話しにもなりました。
だから、今すぐじゃあ行こうという話にはならなかったんですけど。そこで小泉さんが入ってきて、自分のタスクを全部引き受けてくれることになったので、自分はフリーになってアメリカに行くことができました。
そういった意味では、彼があのタイミングで入ってこれたのが、メルカリが比較的早いタイミングでアメリカに行けた理由の1つになります。
うまくいかなかったアメリカ進出初期
手嶋:亮がアメリカに移住したタイミングと、サービスインのタイミングっていつだっけ?
石塚:移住したのが2014年の3月です。
手嶋:そんなに早く。じゃあCMの前にもう移住してたんだ。
石塚:そうですね。アメリカ法人を2月に登記して、3月に移住して4月から人を雇いはじめて、サービスインしたのが8月だったかな。それはステルスリリースだったんですけど、まずはリリースしたのが8月ですね。
手嶋:それはほぼ日本と同じUIで1回出したんだっけ?
石塚:そうですね。とりあえずは日本とほぼ同じもので変更は最小限にとどめて、これがどれくらい通用するのかやってみようという感じで出しました。
手嶋:俺も覚えているのは、進太郎さんは究極日本が失敗してもアメリカが成功すればいいんだとか、アメリカに社内のリソース9割寄せますとか、いろいろなことを表現を変えながら、とにかくアメリカやるんだということを言い続けて、その流れでトミーもアメリカに完全シフトってことになってたんだよね。全社的にもうアメリカに注力することになって。
富島:それでいうと、結局そこらへんってなんでそういうふうになっていったかというと、なかなかうまくいかなかったからという話なんですよね。
手嶋:アメリカがね。
富島:さっき2014年にアメリカのサービスとかをリリースしたとき、当然日本の開発とアメリカの開発を両方やっているので、日本版と同じUIだとはいえ、裏側とかはかなり開発がものすごく必要だったし、多言語化するのもけっこう大変だったりして、ほぼダブルワークみたいな感じだったのでかなり大変でした。
日本はさっき前半で話したとおり、CMを打って、手数料も開始して、それなりにうまく立ち上がりはじめていたので、アメリカにもうちょっと自分たちのマインドを向けることはできていたんです。ただ、思うように全然いかない。
当然、日本とアメリカ両方やることでいいことの1つは数字を完全に比較できることですけど、どう考えてもアメリカのほうが、いろいろな各種数字が悪いわけですよね。なので、いろいろやり方を変えなきゃいけないと。
まずは、プロダクトチームも自分たちが行くことが重要だよねと、まずアメリカに行く中心メンバーみたいなのを決めて、それで中心メンバーだけ行きはじめる。且つそれに合わせて全体的にアメリカ出張みたいなのも増やして、やっぱりみんな現地で1回使ってみないとわからないよね、みたいな感じとかを徐々に徐々に始めていったんです。
それでも一応伸びてはいるけど、とてもその先にすごくうまくいくというような感じはなくて。ある意味では日本版というのは、いろいろ苦労はあったけれども、アプリの企画という意味では最初のものがけっこう当たったという感じだと思っています。
でもアメリカはそうではなかった。
ただ、ここらへんは自分自身の反省も含めてなんですけど、地道な改善もするけども、それだけじゃ難しいよねと。明らかに角度を変えるためには、大きなクリエイティブな解決策が必要だよねという、一発逆転とまではいかないですけど、そういう発想にはなっていて。
なので、アプリ自体のいろいろな企画とか、機能とかも、根本的に変える必要が何かあるところがあるんじゃないかというのを探すのもそうだし。アメリカ事業への取組み方というのも、根本的にやり方を変えないとけっこう難しいんじゃないかという話をする中で、9割アメリカにプロダクトチームはリソースを振り分けるという感じの流れになっていくんです。
手嶋:あのときって実際9割振り分けてた?
富島:そうですね。開発は、という意味なんですけど。
日本版はたぶん3、4人くらいかな。そこはすごく大変だったと思うんです。結局全社的なプライオリティというのはアメリカですというふうになっていて、ただ日本版は確実に伸ばさなきゃいけない、リソースはありません。その中でどう伸ばすかという感じだったので。
ただ彼らが開発した機能とかで伸びていたので、それはすごいなと思うと同時に、アメリカはなかなかうまくいかないので、申し訳ないなじゃないけど、そういう感じのことは思っていたりしましたけどね。
日米でソースコードを使い分ける決断
手嶋:まあ全部だと思うんですけど、亮とか、今振り返るとこれやっぱ大変だったなとか、もしくは、今だったらもっとこううまくやれたのにとか、アプリそのものについてでもいいですし、会社経営全般のどういう要素でもいいんだけど、なんかある?
石塚:大変だなと思ったのは、日本とアメリカで分かれて開発している。かつ、日本とアメリカでソースコードも同じで、当時はやっていて。そこが一番大変という意味ではそこが大変でした。トミーとかは特にそこがすごい大変だったと思うんだけど。日本はすごいうまくいっていて伸びているし、ちゃんとマネタイズもできていて、収益も上げていた。実際、そこの日本の収益を上げていかないと、アメリカに投資するお金もないわけなので、そこはどんどん伸ばしていかなければいけない。
だけど、アメリカのほうはアメリカのほうで、とりあえずまずは日本のものを出してみて、でもそれがその場ではうまくいかなかった。なのでいろいろ変えていかなければいけない。だけど、本当にもうガラッと違ったものにしようとすると、日本版とのソースコードを共有しているので、ガラッと変えることが非常に難しい。さらにいろいろとガラッと変えてしまうと、日本のほうに良からぬ影響が出てしまう可能性もある。そうすると、ちゃんと収益を上げているところもうまくいかなくなってしまう可能性もある。そういったところのコンフリクトがすごい大変だったなと思います。
あとは、日本とアメリカとでチームも分かれていて、今ではメルカリは英語公用化が進んでいて、実際に英語でもコミュニケーションが取れる環境にはなってきているけど、当時はまだそこまでではなかったので、日本のスタッフとアメリカのスタッフがコミュニケーションを取るというのもけっこう難しかったんです。社内で通訳専門の人を雇ったりとかしていて、そういった人にミーティングに入ってもらったりとか、仕様を全部訳してもらったりとかしていたんですけど、それでもけっこう大変でした。そこのコミュニケーションとか、あと、ただ単に相手の言っていることがよくわからないというだけじゃなくて、なんでそういったことを言っているのかという、背景とかもなかなか理解されないんです。
例えば「ここの機能をこういうふうに変えたい」とかって言っていても、なんでそんなこと言ってるのかわからねえよ、みたいなこともよくあったので。そこをどう円滑にコミュニケーションを取るようにするのか、スムーズにおこなうのかというのは難しかったですね。
手嶋:ある日確かに取締役会の議題で、「日米のソースコードを分けます」というのが、正直投資家としてはそこまでの解像度だとあまり気にしていない話じゃない、普段は。
石塚:まあそうですね。
手嶋:突然ソースコードの分離というのがものすごい重要なテーマとして出てきて、深い議論がなされていたんだけど、あれは、亮が言ったジレンマを解決するために決断したんだと思うんだけど、あれってやったんだよね?
石塚:そうです。
手嶋:あれは誰が言い出したの? あれもすごい労力がかかるわけでしょう。日米のソースコードを分けるってこと自体。そういう状況の中で誰がやろうって言い出したの?
石塚:最初はトミーですね。
手嶋:言い出しにくい雰囲気とかはなかったの? 「ええ? ソースコード分けるの?」みたいなのって当時なかったの?
富島:エンジニアとかはそれを望んでる人が多かった気がします。まあ望んでない人もいるけど、やっぱり現場で働くときに大きなストレスになってたのはあるんですよ。ソースコードが一緒がゆえに、ちょっと日本とアメリカでお互いにストレスかかる状況というのは常に存在してたので。
ただ、それに対するデメリットも当然あって、日本チームの人が簡単にアメリカの機能開発に入ってこれなくなるとか。今まで日本とアメリカ一体で頑張っていたのにこれから別々なの?というのもあるし。あとは、特に労働環境みたいな意味とか、気持ち良く働くとか、アメリカに対する機能開発のスピードという意味だと分けたほうがいいんですけど、それって結局は環境整備みたいなところに近いんです。だから、経営的な決断でいうと、それをやったからといって、新しい機能がつくれるとか、そういう話ではないんです。
だから、それが直結しないところが、そもそも提案すべきかどうかとか、決断すべきかどうかというところに最大に悩んだところですけどね。
手嶋:確かに経営者として説明責任が果たしにくいってことだよね。なんのためにやるの?みたいなことでいくと。亮とかは全責任アメリカで当時は背負ってたから、やってはほしいけど今トミーが言った文脈でいくと、やったとこで結果出るかわからないし、当時、ソースコードの話でいけば言い出しにくいみたいなのはあったの?
石塚:そうですね。トミーも言ったように、それでじゃあソースコードを変えたから、じゃあそれでアメリカ事業うまくいくとかっていう確約は当然ないわけで。
なので、そういった意味では、それをやってどうなるの?というのは当然あるんですけど。ただ、今のこのやり方でアメリカがうまくいくめどがまったくない。アメリカをどうにかするんだったら、もっとドラスティックにプロダクトを変えなきゃいけない、やり方を変えなきゃいけないとは思っていて。
だから、ドラスティックにやるとなったら、日本版と大きく変わっていってしまうので、今のようにソースコードを分けた形で、ドラスティックにもっとアメリカのアプリを変える。それこそフリマアプリだけど中身はまったく違うものになる可能性もあって、それがソースコードを維持したままできるのか。さらにいえば、ソースコードが同じになっていることによって、ドラスティックに変えるという判断が弱くなってしまうんじゃないかというのが、そういった懸念があったので、最終的には分けたほうがいいという考えになりました。
そこは、当時トミーと一緒にアメリカにいたので、いろいろと話をして、帰りトミーをよく自分が車でトミーのアパートまで送っていって、その間にいろいろ話すということをやっていたんですけど、そういったところで、そうやってソースコードを分けないとドラスティックに何かを変えないとどうにもならないよね。それをするにはまずソースコードを分けないといけないんじゃないかというような話は、トミーと自分の間ではその話が先に進んでいたんですよ。ただ、それを他の経営陣と共有するというところまではまだやっていなくて。
山田氏のアメリカCEO就任とジョン氏の参画背景
手嶋:2人だけアメリカにいてその当時、他の経営陣は日本にいたんだ。
石塚:じゃあそこをどういうふうに話をするのがいいのかで、そもそもそれをやったほうがいいのかねという懸念はありましたね。
手嶋:トミーが起案をして、結果それじゃあやろうとなって。今のUSの状況の1 つの大きなターニングポイントにはなったんだろうなということですよね。
富島:そうですね。それがニアリーイコール、現地でプロダクトの人も積極的に採用していくという方針とかにつながっていくというところです。
手嶋:アメリカはもう社運がかかっていて、9割寄せているみたいな。究極日本で失敗してもアメリカで成功するみたいな中で、途中で進太郎さんが、だったら進太郎さんがCEOをやるべきだよね、みたいな流れの中で、小泉さんが日本では社長になって。
今もアメリカでCBO、メルカリのディレクターをやってくれているジョンが入ってきてという流れになるんだけど、まずジョンが入ってくるよって、これまたさっきの小泉さんの話みたいに、いつどういうタイミングでどう聞いたんですか? 誘ったよ、みたいなのは聞いてたの?
石塚:自分は一緒に誘ってたんですよ。常にアメリカにいたのは自分だったし、ジョンとは前々から知っていたので。
実際に彼が入るよという話を聞いたのが2017年ですよね。ただ、それまでの過程はいろいろと、進太郎さんとどういう話をしているのかというのも聞いていたし、自分との話で感触とかもわかっていたので、入るよとなったことに驚きはなかったんです。
あと、進太郎さんがCEOになって、その後にしばらくして、今度ジョンがCEOになって。体制がいろいろと変わっていた時期だったんです。ただ、進太郎さんがCEOになることによって、それで何かすごいガラッと変わったということは結果的にはなかったんです。彼は常にアメリカにいるというわけでもなかったし。
ただ、そこですごいジョンが進太郎がそこまでコミットするんだったら、US事業もメルカリは本当に本気なんだなというのを、彼はそこで認識したらしくて。なので、進太郎さんがCEOになることによってジョンが入ってきた。それがすごい一番の大きな変化だったなという気はします。
手嶋:コミットメントを示せたということですね。トミーはジョンが入ってくるよって、大体並走して聞いてたの?
富島:そうですね。それは聞いていて。僕は前々からはジョンのことを知らなかったので、誘っているという過程の中で知りました。
さっきの進太郎さんが一瞬CEOになった、みたいな話でいうと当然結果論としてジョンがその後テイクオーバーしてくれたからそういうふうになっていくという感じですけど、自分は進太郎さんにずっともっとアメリカのコミットを増やしてほしいなと思っていて。
やっぱり最初に日本がうまくいった要因の1つは、進太郎さんがプロダクトとかも含めて、深くまでコミットしてたからというのも当然なんですけどあるわけです。
アメリカでなかなかうまくいかない中で、そこで進太郎さんがコミットを増やすことで、何かいい効果があるんじゃないかなというふうには思っていたので、そこ自体はすごい、僕としてはかなり歓迎していました。
アメリカ事業の黒字化について2人の感情
手嶋:先日、ついにアメリカ黒字化しましたよね。
黒字化ということにどういう意味を感じるかというのは人それぞれなんだけど、少なくとも、我々が当時それぞれの立場で当事者として関わっていたメルカリのUSの状況でいくと、立ち上げがすごい大変だったと。
そういう紆余曲折もあったということからするとすごいことじゃないですか。黒字化したというニュースを見て、亮とかは、どう感じたとか、思ったとかはある?
石塚:率直にうれしいのと、ちょっと複雑だなと思うのと両方ですね。
手嶋:それは自分ができなかったから?
石塚:そうそう。やっぱそれを自分がいるときに成し遂げたかったなというのは当然ありますね。
手嶋:トミーは?
富島:そうですね。まあ一緒ですね。
手嶋:退任した会社というのは大体そう思うよね。成長してくれてるとうれしいけど、自分がやっぱり関わっていない、関わりをやめた後も成長し続けると、みんなそういう気持ちにはなったりすると思う。
富島:あとは、時間がある程度辞めてから経ってるので、少し客観的には見れるようにはなってきていて。
自分が成し遂げたかったというのもあるけど、当時の自分の実力というものもあると思っていて。やっている最中はあんまり自分の客観的な実力ってよくわからないところもあるんです。自分自身はもっと成長できると思ってやっているので、仮に今足りなくてもすごくなれると思ってやっているから。
けど、自分の実力が客観的に足りていないところもあったなというのは、今にして思うと思いますけどね。特にアメリカのプロダクトのトップとしての、プレーヤーとしての動きというと。
手嶋:亮はなんかもう少しある?
石塚:トミーの言ってるようなところも当然あるけど。また悔しいなとか、自分がいるときにやりたかったなというのもあります。
ただ、同時に今USに関わっている人たちも当然たくさん知っていて。彼らはすげえ喜んでるだろうなとかって思って、やっぱり自分のことのようにうれしいですね。
手嶋:僕はもう本当にうれしいですね。2人が原石みたいな状態をまずつくって、それをジョンが、ある種引き継いで、コロナとかもありつつもサクセッションしてくれて。
だってあのとき黒字化ってイメージがつかなかったもんね。僕は2017年くらいまでしか関わってないんですけど、それはすごいリスペクトですよね。
亮もトミーも含めて、関わった人に全員リスペクトだなと。日本のインターネット業界の関係者としては、僕はそう思いますという感じです。
お二人の退任後の生活
手嶋:最後に、最近何をやっているんですか?みたいなことを聞きたいんですけど、亮は退任してもう3年くらい経つ?
石塚:そうですね。2019年なので、2年ちょっとかな。
手嶋:何やってるの? 最近は。
石塚:今はアメリカのシアトルというところに住んでいて、こっちでいろいろなスタートアップにエンジェル投資をしたりとか、あとはアクセラレータとかでメンターとかをやって、いろいろなスタートアップにアドバイスをしています。
手嶋:USのスタートアップのほうが多いの?
石塚:主にUSですね。いくつか日本のほうにも投資をしています、手嶋さんと一緒に。
手嶋:そうですね。私とはCatlogという猫の事業で投資させてもらったんですけど。基本的には今後もそういうスタートアップの一番の理解者とか支援者みたいな立場でいろいろな仕事をしていこうかなというプランですか?
石塚:そうですね。少なくともアメリカのスタートアップに対してはそういった感じで、自分がこれまで経験したこととかをいろいろと次につなげていくということをやっていて。
日本のスタートアップに関しては、さっきも言ったとおり日本のスタートアップにもいくつか出資をしていたんですけど、ここに関しては海外、特にアメリカに進出している、もしくは今後本気でやろうと思っているという会社に対して応援してあげたいな、ヘルプしてあげたいなという思いがあって。
手嶋:亮にエンジェル投資してもらいたかったら、アメリカとかを本気で考えていれば連絡頂戴という感じ?
石塚:そうですね。日本国内だけというところだと、たぶん自分がそこまでヘルプしてあげられるということも少ないし。
なので、アメリカとか海外でやりたいという人に対しては、これまで自分がメルカリでやっていたこととかは、結果的にそんな自分がいる間に大成功したわけではないけど、でもこれまで自分が経験したこととか、陥った技とか、そういったところはいろいろと共有できるかなと思うので。
手嶋:ぜひ聞いてくださっている方で、アメリカを本気で考えている人は何で連絡すればいいの?
石塚:Facebookとかでもいいですよ。
手嶋:トミーは今どこに住んでるんだっけ?
富島:今は東京なんですよ。
手嶋:戻ってきたんだ。今、何やってるんでしたっけ?
富島:今は、最近忙しくやってるのは、山田進太郎D&I財団の立ち上げですね。
手嶋:それっていつ頃誘われたの?
富島:3月くらいです。
手嶋:いきなり連絡が来たの? 進太郎さんから。
富島:そうです。「ちょっと話さない?」みたいな感じで。ドキッとするじゃないですか。
手嶋:進太郎さんに言われるとちょっとドキッとするよね(笑)。
富島:いいことなのか、悪いことなのかわからないし(笑)。
手嶋:それでZOOMか何かで話したの?
富島:そうです。メルカリ始めるときと一緒ですよね。
「こういうことをやろうと思ってるんだけど」といって、比較的自分も時間に余裕があったので、というのもあるし。去年コロナとかで、自分もいろいろ寄付とかも去年からいろいろやってて、非営利っぽいものに対する取組み方というのは、寄付は寄付で今後も続けていいんだけど、やっぱり自分でもう少し関わって何かできることってないのかな?というのは思っていたりはしていたんです。
それがこういったD&Iとか、女性のSTEM分野とかっていうことは当然思っていなかったんですけど、もうちょっと社会貢献的なものを何か自分でもできないかなと思ったようなタイミングではあったというところですかね。
手嶋:トミーは財団の中で、今どういう役割というか、具体的にはどういうことをやっているの?
富島:一応公式には評議員ということになっていて、評議員というのは、株主みたいなものですね。
ただ、株みたいな組織ではないのですが、それが公式な立場です。一応プロジェクトマネジャーみたいな感じかな。奨学金をどういうふうな設計をして、どういうふうに募集してとか、あとは今だとどういうふうにより多くの中学生の女性の方に対してこの奨学金を知ってもらうかとか、そういったこと全般ですよね。
手嶋:メルカリという会社としても、今D&Iをかなり意識して取り組んでいて。進太郎さんもその流れの中で、D&Iというのをテーマにした財団を今回やったと思うんだけど、進太郎さんはD&Iということに対して、ここ2、3年くらいで急速に意識がフォーカスしてきたという感じになるのかな?
富島:もうちょっと長いかもしれないですけど。まあいろいろな文脈があるとは思っていて。
メルカリという観点でいうと、日本のメルカリに外国人のエンジニアがたくさん入ってくるようになったというのと、それがうまくいったというのは大きなターニングポイントだったと思っています。
特にはインドの方をたくさん新卒採用したというところから、実際にそれで日本の会社のプロダクトチームの働き方とか、当然仕様書とかも全部英語になったりとかも含めてなんですけど。それが本当にインクルージョンされていって、プロダクトチームとして強固になっていったという。
だから、いいことをしようというのもあるけど、会社の事業観点でいってもすごい良かったというのが直接的に結びついているというところはありますよね。
ただ、一方で、女性のソフトウェアエンジニアみたいなことでいうと、いわゆる転職マーケットみたいなところでいったってそんなに多くないわけです。そもそも母数が少ないという話があって。結局、外国人エンジニアをなんで入れようかという話になったときは、日本ってメルカリが求めている人材をさらに増やしていくにあたって、日本だけだとパイが少ないよねという話から来ているところはあって。もちろん外国人の人の観点で、ダイバーシティで強くなるという面もありましたけど、そういった、単純にパイを増やすみたいな意味もあったと。
女性でいうと、もちろんメルカリを使ってくれている方の半分以上は女性なわけですし、女性のソフトウェアエンジニアが多くいるというのは、本来的には当たり前のようにあってしかるべきだけど、採用しようと思ったって、そんなにそもそもいませんよねという話はずっとあるんです。
結局それを根本的に改善するためには、もっと早い段階から手を付けなきゃいけないですよねということになり。でも、それって会社でやることじゃないよねというところから、進太郎さんが個人で財団をやるという話につながっていったんですよね。
手嶋:今回は理系の女子学生を積極的に支援して増やしていきたいということだと思うんだけど、財団的にはD&Iという枠組みの中で、今後もいろいろ企画していくの?
富島:そうですね。ただ、今ちょっとこれにフォーカスしているので、まだ次何やるかというところまでは決まっていない。
あと、僕も進太郎さんもまったく土地勘もないですから。この非営利なところもそうだし、奨学金もそうだし、そういった学校教育関係者とかの知見があるわけでもない。
なので、これを一度やってみて、その結果を見て、次どう動いていくかというのをまた改善していくという感じにはなると思います。
手嶋:まだ募集しているんだっけ?
富島:そうです。一応9月末までなのですが。これを聞いている方にお願いしたいのは、インターネットで、例えばアプリをリリースしましたとか、サービスをリリースしましたって、けっこうさっきの話じゃないけど、広告で告知したりとか、SNSで頑張るとか、それだけである程度届く人には届くのかなというところもあるんですけど、僕らが今やっていることって中学生の女子、中3の女子がターゲットなんです。
それってけっこう直接声を届けることがかなり難しい。直接SNSを見ている人もいれば、親経由とか、先生経由とかだったりするんですけど。なので、それなりにもうすでに応募は来ているんですけど、告知の方法というのは難しくて。
なので、少しでも知っている方にシェアしていただくのもそうだし、SNS上でつぶやいていただいてもいいんですけど、そういった形で応援してもらえると、理系を志す女性の方が増えて、それが最終的にはいつか、これを聞いている人、インターネット業界の人が多いと思うんですけど、自分たちの事業にも跳ね返ってくると思うので、そういうシェアをしていただけるとありがたいなというふうには思っています。
手嶋:このPodcastの概要欄に山田進太郎D&I財団のURLを載せておくので、ぜひ聞いた方は見たりシェアしてもらえれば。
あとは近くに、中学生か小学生の女子がいる家庭があったら教えてもらって、こういうのあるよと言ってもらえたらなと思います。
富島:ぜひぜひお願いします。
手嶋:では今日はメルカリの共同創業者の富島さんと石塚さんにいろいろ、特に創業期の話とアメリカの話にフォーカスして、貴重なお話をありがとうございました。
大変、聞いている方も面白い話ができたんじゃないかなと思いますので。また、これがちゃんとシリーズで続けることができたら、2年後くらいにまた、最近どうなの?みたいなのができたらなと思います。お2人とも今日はありがとうございました。