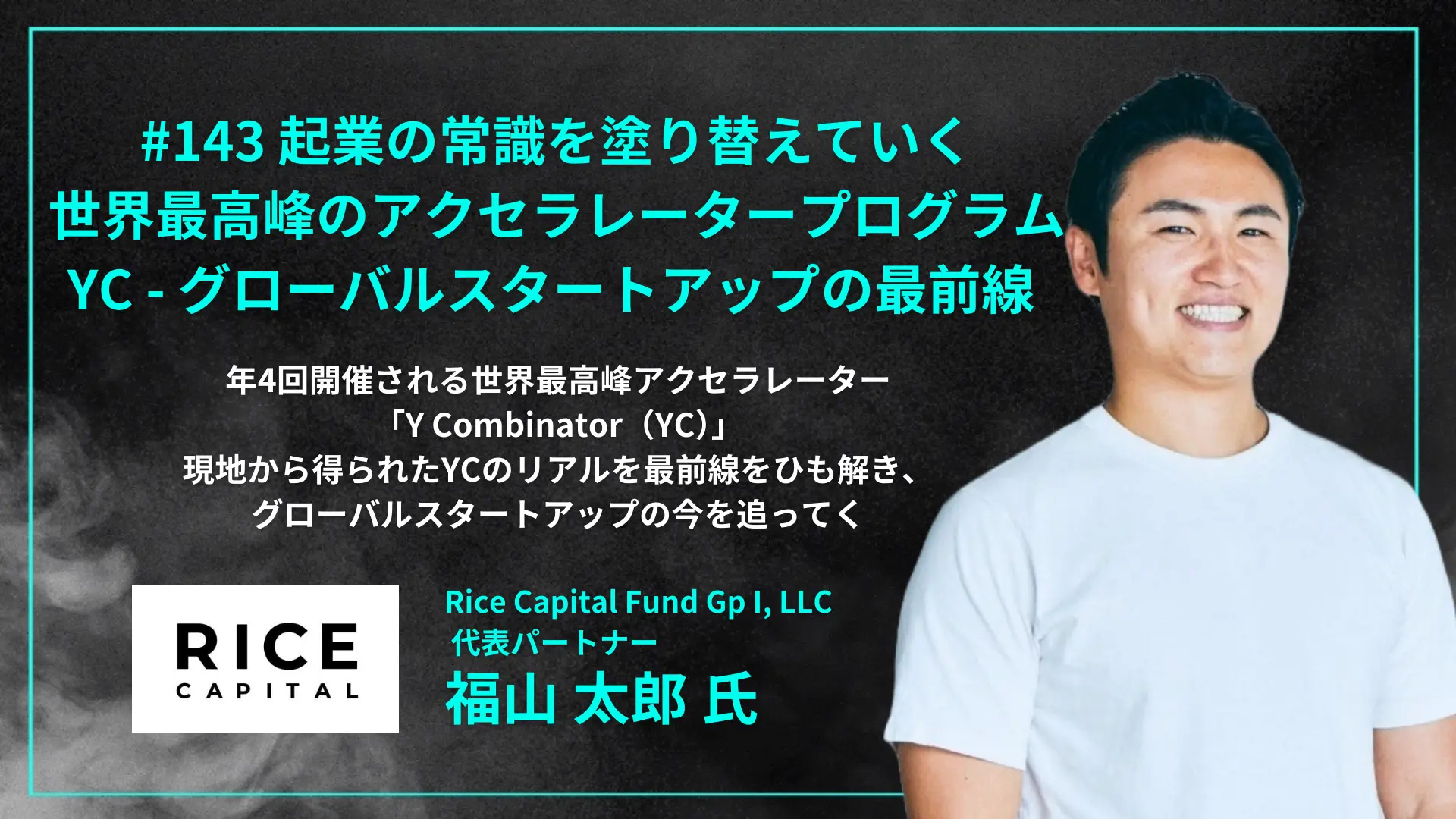#7 サイバーキャッシュ本社の破綻やSBI子会社としての再出発──フィンテック20年の歴史を振り返る ー ナッジ沖田貴史氏

「スタートアップ オフレコ対談」は、XTech Venturesの代表手嶋とゲストの方をお呼びして対談する番組です。今回はフィンテック歴20年、ナッジ株式会社代表の沖田氏をゲストに迎えます。学生時代からフィンテックスタートアップ「サイバーキャッシュ」(現ベリトランス)の立ち上げを行い、マザーズ上場後、代表に。
クレジットカード情報をネットに入力するのも怖いと言われた時代でのフィンテックスタートアップを立ち上げています。前半では当時珍しい香港上場を行った経緯や、経営統合を繰り返した背景を振り返っていただきました。
スピーカー
・沖田 貴史 氏(@OKITATakashi)
ナッジ代表取締役
・手嶋 浩己(@tessy11)
XTech Ventures代表パートナー
※記事の内容は2021年11月時点のものです。
学生時代からフィンテックスタートアップに関わったきっかけ
手嶋:今回は、フィンテックスタートアップであるナッジの社長で、起業家の沖田さんをお招きしています。実は私と沖田さんは一橋大学出身の同級生。ですが、知り合ったのはここ5〜6年前ぐらいで、大学を卒業して十数年経ったあとに仲良くなったんです。
学生時代に飛び込んで、これまでイノベーション産業、そしてスタートアップ産業一筋でやってこられたのが沖田さん。過去の経歴も含めて聞いていきたいなと思っています。まず簡単に自己紹介と、今までの経歴をさらっとお願いします。
沖田:沖田です。今回はこういった機会をいただきありがとうございます。手嶋さんとは仕事よりもプライベートの方が付き合いが長かったりするので、怖い質問をされないかなとヒヤヒヤしてるんですけれども(笑)。
まず簡単に自己紹介させていただくと、大学在学中にベリトランス、当時はサイバーキャッシュというアメリカの会社とソフトバンクのジョイントベンチャーだった会社の立ち上げに関わりました。
「フィンテック」という言葉がない頃から、20年以上この世界にいます。最初の10年は、どちらかというとeコマースのインフラを作る立場で、日本国内の決済インフラを担当していたんですけど、その後はアジア市場にシフトをして、直近はブロックチェーンで金融機関を作っていました。
2020年の2月からナッジという会社を立ち上げました。チャレンジャーバンクと言っています。第1弾のサービスとして、提携カードを1枚から実現できる「ナッジ」というサービスを9月からスタートしています。よろしくお願いします。
手嶋:僕からすると、沖田さんはもう日本のフィンテック産業の生き字引的存在です。フィンテックをさまざまな角度からやってきて、いよいよ自分で起業されました。沖田さんの見ている世界を垣間見せてもらって、フィンテック産業に対する見方も皆さんに伝わるといいかなと思っています。
まず大学生の時に、現・DGフィナンシャルテクノロジー社が手がけるベリトランスという決済サービスの日本の立ち上げに関わっていますよね。1998年ぐらいですかね、大学4年生のときに関わり始めて。
ネットプライス創業者で、現在はビーネクストというVCを設立した佐藤輝英さんと一緒にやっていたと認識しています。当時の一橋大学生って、僕も含めて国立でみんなぽわ〜んと過ごしていた人が多い中で、なぜ突然そういうスタートアップの世界に飛び込んだのか。そのきっかけを教えてもらえますか。
沖田:きっかけは偶然です。たとえばHENNGEの小椋さんとかは、当時から「学生起業家」って感じでやってらっしゃいましたけど。起業家というのは自分からはすごく遠い存在でしたし、全然そんな気はなかった、というのが本音です。
手嶋さんと同級生なので、1995年に大学に入学して、Windows95がまさに出るときが1年生の終わりぐらいですよね。僕は石川県の出身なので、東京に出てきて最初の頃は非常に大学生らしい暮らしを楽しみました。
手嶋:楽しかったですよね。
沖田:全然勉強せずに遊んでました。そこにインターネットが登場して、とりあえず触ってみたのが1年生の終わりぐらいですかね。最初はそんなに強いインパクトはなかったんですよ。
当時の大学生って、携帯電話も持っているか持っていないかくらいの時代。今はもう懐かしいですけど、僕はPHSを持っていて、そういったテクノロジーみたいなものは割と好きなんですけど、別に理系でもないし、インターネットに最初に触れたときもピンときたわけじゃなかった。ただ、なんとなく「これって世の中を変えていくんじゃないかな」と、ぼんやり感じたのが最初ですかね。
手嶋:それはいち消費者、いち大学生としてですよね。そこから、なぜベリトランスの立ち上げに関わることになったのでしょうか?
沖田:当時は一応、経営情報システムのゼミを取っていたんですよ。
手嶋:ちなみに、現在マッキンゼーの日本支社長である岩谷さんも、そのゼミに同級生でいたんですよね。伝説のゼミですよね。
沖田:そうです。ゼミには2〜3年ぐらいしかいなかったんですが、濃いキャラの人たちが上にも下にもいましたね。そこでインターネットを研究テーマにしていました。インターネットにもいろいろあると思いますが、商学部にいたので何かしらビジネスをやりましょうと。国立音大が近かったんですが、楽譜を海外から輸入するのが大変だという背景から、それをインターネットで売ったらニーズがあるんじゃないかと話をしていたんですよ。
当時はヤマトもあればゆうパックもあるし、物流インフラは今とそこまで変わらない。でも、キャッシュが主流なので、現金をパソコン通じて渡せませんよねっていう、めちゃめちゃプリミティブな問題に直面して。当時はeコマース=決済みたいな感じだったんですよ、アカデミック的なアプローチだと。そこで、決済手段としての電子マネーが当時の流行だったので、電子マネーを研究テーマにしたんです。さっき出た岩谷とかと皆でイギリスに行って、現地へ路上でヒアリングして調査したりとか。
手嶋:そんなことまでやってたんですね。
沖田:手嶋さんもご存知のように、僕もグローバルでやってきたし彼も今でこそマッキンゼーのトップですけど、2人とも当時は英語が全然できなかった。なのによくそんなことやってたなと思うんですけど。
そのときに、世界最大のネット決済のサイバーキャッシュが日本にいよいよ来ますというのでインタビューしに行ったら、さっき名前を出していただいた佐藤輝英さんが終わったあとに来て「沖田くん、暇なら手伝ってよ」と話があって。当時もう4年生で、就職活動も終わってたので暇です、と。
だから、熱く起業しました!とかではなくて、手伝ってと頼まれたのでやりましたみたいな、のほほんとした感じで最初は始めています。
サイバーキャッシュ本社が破綻。SBI子会社としての再出発
手嶋:そのとき佐藤さんは社会人1年目で、会社員としてサイバーキャッシュに関わってたんですかね?
沖田:そうです。けど事実上のトップは彼みたいな状況で。もう1人、石谷さんという今ナッジのボードメンバーになってもらっている人がいるんですけど、石谷さんも佐藤さんと同級生で、事実上は学生3人でやっている感じでしたね。
手嶋:そのとき沖田さんは大学4年生。私なんかはそういう世界があるとも知らず、国立で暮らしながら普通に就職活動して、広告代理店とかに入っていったわけですけど。沖田さんは就職活動をしなかったってことですかね。
沖田:就職活動はしたんだけど、就職しなかったんですよ。
手嶋:なんでですか?
沖田:まあ、就職する前に転職しちゃったみたいな感じなんですけど。一番大きいのは、やっぱり今言った2人がやっぱりすごい能力高かったんですよね。自分はそれなりに能力があるんじゃないかと、学生時代にはちょっと鼻っ柱高くなってたんですけど。サイバーキャッシュはアメリカの会社だから英語でコミュニケーションしなきゃいけないんですけど、そもそも何を喋ってるのか全然わからないんですよね。技術面のこともわからないし、ビジネスの話も全然2人に敵わなくて。びっくりするぐらい自分でできないなって思ったんです。この人たちと働いているとすごく悔しいけど楽しくて勉強になるし、もっと一緒にいたいなと感じたんですよ。
だから、eコマースとかネット決済とか電子マネーとかっていうテーマ性うんぬんではなくて、こういった極めて優秀な人たちと一緒に仕事するのは自分の成長という観点でも良いことだし、もっと言うと単純に楽しいなと。内定先の会社には本当に申し訳なかったんですけど、入社を辞めますと。
手嶋:なるほど。スタートアップに入るのって、今よりおそらく100倍ぐらい抵抗があった時代だと思うんで。当時の自分だったら、いかに優秀な人と一緒に働けるとしても正直考えられなかったですね。
で、その後もそのままどっぷり入ったあと、サイバーキャッシュ、今のサービスで言うとベリトランスですけど、これはどうなっていったんですか?
沖田:社会人になりました。2年目にアメリカの会社が潰れました、と。
手嶋:あ、本社が潰れたわけですね。
沖田:そうですね。今は懐かしいネットバブルの頃だったので。
手嶋:そういうサービスって結構ありますよね。エキサイトとかも今、日本法人は残ってるけどアメリカ法人は潰れちゃったりとか。サイバーキャッシュもそうだったと。
沖田:それはそれですごく勉強になったんですけど。サイバーキャッシュ自体、時流も掴んでいたし、優れたメンバーが関わっていたんですけど、事業のピボットがちょっと早すぎたり遅かったりして破綻しちゃいましたと。破綻した当時、日本側では全然ビジネスが始まっていませんでした。2001年で、当時まだeコマースが全然使われてないか、もしくはECをやっていても結局ネット通販なんですよ。決済とかも代引きでした。
手嶋:クレジットカードの情報を打ち込むのが怖いみたいな時代ですよね。
沖田:そうです、怖いっていうかもう打ち込んじゃいけませんみたいな。インターネットそのものが怖いんですもん、だって。だから、日本側も全然うまくいく感じはなかったんですよ。当時サイバーキャッシュの日本パートナーがソフトバンクだったので、孫さんと現・SBIホールディングス代表の北尾さんとで決めたんですけど。当時は北尾さんとアメリカの人間と2人の共同代表がいました。
サイバーキャッシュサイドはもう潰れててんやわんやなので、「もう日本もダメだと思うので、日本側も事業を畳みますか」と北尾さんに相談しに行ったんです。そのとき、北尾さんはあまりピンときていなくて「eコマースっていうのはそもそもこれからどうなるんや。時代は来るんか」と、ばくっとした質問をされて。それに対して、「時代はやってくると思います」と。1〜2年の話ではないかもしれないけど、ネット上で物の売り買いもするし、旅行の予約とか、そういったものも普通になると思いますよ、という話をしたんですよね。北尾さんも「そうか」と。「ところでお前頑張ってるか?」って言われたんですよ。
当時まだ20代前半じゃないですか。今言うとちょっとまずいんですけど、夜中の2時3時とかまで普通に働いていた時代。「そのぐらいやって頑張ってます」って話をしたら、10秒ぐらい北尾さんが珍しく黙ってちょっと考えたあとに、「じゃあもうちょっと頑張ってやってみ」と言われて。それで、当時10億ぐらい調達したんですけども1〜2億円くらい減っていたことを伝えたら「じゃあもうちょいあってもいいな」って追加出資ドンとしてくれて。アメリカの株も買い取って、子会社として再出発したのがちょうど2002年ですね。
手嶋:そのときはソフトバンクから離れてSBIという会社が存在したときですか。まだ金融部門のとき?
沖田:厳密に言うと、まだソフトバンクファイナンスっていう社名のときですね。
手嶋:その後、ソフトバンクファイナンスがSBIグループとして独立した流れで、当時のサイバーキャッシュもSBIグループになっていくんですね。北尾さんから期待をかけてもらって、拾ってもらって。その後、世の中の変化とともにベリトランスの事業はどうなっていったんですか?
沖田:おかげさまで、私の予想を良い方向に裏切って、その後2年で黒字になりました。2004年にIPOしたんですけど、当時eコマースのIPOって多かったんですよ。さっきのネットプライスもそうですし、ゴルフダイジェスト・オンラインさんも。あの頃が、ECのIPO第1世代みたいな感じでしたね。
手嶋:上場はSBIのグループ会社として?
沖田:はい。子会社上場で、当時あった大証ヘラクレスに上場しました。ちょっといろいろあったんですけど、結論としては翌年、上場した直後の総会で正式に代表取締役になりました。
手嶋:そこで上場会社の社長になったと。ヘラクレスの。
沖田:そうですね。
手嶋:なるほど。ちなみに時間軸でいくと、大学生のときに「すげえ」って言ってた佐藤輝英さんはサイバーエージェントの藤田さんにヘッドハンティングされて、2000年にサイバーエージェントグループとしてネットプライスの代表に就任すると。なので、佐藤さんも沖田さんも、グループ会社の上場社長に数年でなっていったという感じですか。
沖田:そうですね、それぞれに道は別れてって感じですね。
ヘラクレス上場会社の社長からアジア事業にシフト、香港上場を行った背景
手嶋:それから日本ではヘラクレスに上場しながら、ベリトランスジャパン自体がアジア事業に傾倒していったんですか?
沖田:そうですね。まあ日本の事業は順調で、毎年3〜4割ぐらいでずっと伸び続けるっていう状態でした。
手嶋:オンライン上の決済手数料で基本は儲けていたということですか?
沖田:そうです。なのでeコマースのマーケットが伸びれば、もうそれがそのまま追い風になって。
手嶋:ベリトランスがeコマースサイトに使われていたと。
沖田:そうです。2008年からはぐっとアジアに舵を切っていて。最初は中国の銀聯と提携するっていうのがきっかけだったんですよ。正直、提携する半年ぐらい前まで、中国には行ったこともなければ、グローバルでビジネスをするみたいな発想はあまりなかったんですけど。当時の中国はeコマースのマーケットも日本より小さく半分ぐらいしかなくて。でもすごくエマージングな状態なんですよね。やっぱり伸びている地域ってすごいなと。
2000年代って、日本が全体的に元気ないわけですよ。一方でインターネットインダストリーとか、eコマースは伸びてるんで、その追い風でベリトランスも伸びてたんですけど。中国は国全体が伸びていて、現地の人々の雰囲気とか感覚もめちゃめちゃ前向きなんですよね。これは非常に面白いというので、中国はちょっとさすがに入りにくいなと思ったんですが、他にインド・インドネシア・ベトナムなどにジョイントベンチャーを作ったり出資したりと、かなりアジアのほうにぐぐっとシフトしました。というのが2008年から2011年ぐらいにかけてですね。
そのときはヘラクレスから統合して、ナスダックにマーケットを移していたんですけど。北尾さんとも議論して、東証1部に鞍替えしようかと。当時、30歳過ぎで、SBIグループの本体の取締役もやってたんですよ。
手嶋:ああ、やってましたね。
沖田:当時、 30代で東証1部の取締役って、ほとんどいなかったんです。ましてや社長だと史上最年少みたいな話だったんで、「おもろいからそうするか」みたいな話があったんですけど。ただなんかあんまりしっくりこなくてですね。いろいろ議論する中で、最終的にはマーケットを香港に移そうという話になり、日本のマーケットからデリストしました。
手嶋:そうすると、SBIグループ時代に、日本の上場マーケットから香港の上場マーケットに移った。
沖田:実際は、その後にデジタルガレージに資本を移してから、香港に上場し直したという流れです。
手嶋:SBIグループからデジタルガレージグループに移ったのは、それぞれのグループ戦略によるものっていう感じの理解でいいんですよね。
沖田:そうですね。そこが最終的に一番大きいのと、あとはデジタルガレージの子会社で、今も事業としてあるんですけどイーコンテクストっていう決済会社があって。デジタルガレージだけではなく、業界再編で何社か合併しようとしていたんですよね。国内で競争するんじゃなくてもう日本では一つになって、日本企業がアジアを制覇しにいこうみたいな議論をしていた。
でも、日本って会社をなかなか売ってくれないじゃないですか。上場会社の社長って、結構居心地がいいんですよね。わりと日本の投資家も緩いところがあるので。そこで、売ってくれないんだったら自分たちの会社を売ってしまえと、売りも買いも一緒でしょうという話になって。デジタルガレージ側と議論した結果、デジタルガレージのほうに株式を移そうということになりました。
手嶋:決済事業として単体で見ると統合したほうが強くなるし、SBIとしてもそれを了承してくれたという構図ですかね。社会人になってから長くお世話になった北尾さんやSBIグループを離れてデジタルガレージのグループ会社の社長に。今は、もう決済事業がデジタルガレージの基幹事業になっていると思いますけど。カルチャーは結構違いましたか?
沖田:そうですね。カルチャーは違いましたし、あと僕は転職したことがなかったんですよ。就職する前に転職しちゃったみたいな感じだったので。
手嶋:内定先を辞退して、ずっとやってるわけですよね、その時点で。
沖田:内定先を断ったのは、自分の中ですごくギルティな思いがあって。あんまりコロコロ転職しないようにしようと思ってたんですよね。だから、そもそも違うカルチャーの組織で働いたことがなかった。
デジタルガレージは林郁さんと伊藤穰一さんと2人の創業者がいますけど、林さんって、まさにインターネット初期の起業家、第一世代の起業家じゃないですか。穰一さんも言わずもがな。北尾さんは北尾さんでパワフルですし、頭の回転も速いし筋も良いし、今でも尊敬していますけど、林さん穰一さんはまた全然違う魅力があるなという感じですね。
手嶋:そうやっていろいろな人に揉まれてきた人生なんですね。北尾さん林さん、伊藤穰一さんっていうね、もうビッグネームが並びまくってるという。デジタルガレージグループのときに、この決済事業会社が香港市場に上場させてもらったっていうことなんですね、
沖田:そうです。正確に言うと、そのときはデジタルガレージに加えて三井住友カード・JCB・クレディセゾン・TISの4社を含めて大株主になってもらって。日本連合みたいな感じで、香港に上場しました。
手嶋:どうでした?香港市場での上場企業の経営経験者ってほぼいないと思うんで、今日本のマーケットに。日本で上場してる感覚とやっぱり違うんですか?
沖田:今上場している会社はそんなに変わらないかもしれないですね。たとえば直近だと、freeeとかマネーフォワードとかIPOしている会社って海外投資家が多いですし、グローバルインフラになり得るので。そういう意味では、今の日本での上場と結構近いと思うんですけど。当時はやっぱり日本のマーケットとグローバルマーケットは相当違いがありましたね。
手嶋:ちなみに些末な話ですけど、沖田さんはその時点で英語はできたんですか?大学時代はできてないだろうとは知っているんですけど。
沖田:最初は念のため通訳を入れてもらっていました。英語は今でも正直言ってちょっと苦手は苦手なんですよ。ただ結局、テクノロジーの世界にいるともう逃げられないじゃないですか。同じようにグローバル化も避けられないので、英語が話せるようにならないと。だからグローバルで仕事しないと無理だねとなったときに、もうマーケットごと移しちゃえば、やるしかないよねと。
手嶋:沖田さんの英語の勉強のために香港に上場したってことですね(笑)。
沖田:そこまで言うと怒られますけど(笑)。
手嶋:いいきっかけになったと。
沖田:そうですね。そのときよく話してたのは、自分のポジションは十分に確立できていたので、苦手なことをやらなくても生きていけるぐらいな感じだったんですよ。だから逃げきりの人生もやれなくはなかったんですけど、やっぱりそれは良くないよねと。
その後ベリトランスを辞めるときに、ブログを書いたときのタイトルが「Beyond my comfort zone」。要は、快適な環境から飛び出よう、と。その第一歩は香港上場あたりだったかなと思いますね。
手嶋:なるほど。2010年代、デジタルガレージグループで、いろんな人と切磋琢磨して、今やデジタルガレージの基幹事業は沖田さんが残していった事業がその1個に当たるって感じですけど。その後、デジタルガレージグループも離れるし、おそらくもっと大きかったのは、大学時代からずっと携わってきたベリトランス自体から離れるという決断ですよね。僕から見ても十分ベリトランスには貢献して、次のステップに行く感じもしますが、直接のきっかけがあったんですか?
沖田:直接のきっかけは、その後に香港市場からデリストするとなったときに、自分の人生を問い直したことですね。別に辞めろと言われたわけでもなくて。
もう20年近くベリトランスにいたので、社員もほぼ全員僕が採用してるわけですよ。事業も自分で作ってきたものがほとんどで、そういった意味ではTHE・創業社長みたいな感じで、めちゃめちゃ快適なんですよね。離れるという選択肢はあまり頭の中にはなかったんですけど、ここで離れないともう一生このままだなと思って。まさに先ほどお伝えした、快適な環境から飛び出てみようという感じですね。
あとちょうど子どもが生まれた時期も近かったので、もう少し家族と一緒に過ごしてもいいかなあとか、人生全体を問い直したときに、思い切って外に出てみようっていうのが大きかったですね。
手嶋:なるほど。ちなみに私が沖田さんと出会ったのは飲み会です。HENNGEという上場企業の社長である小椋さんが僕らの大学の1個上で、僕が小椋さんと大学生の頃から知り合いだったんですが、当時、僕がメルカリの投資家としてメディアに出るようになって「手嶋さんって広告代理店にいませんでしたっけ?」と突然連絡をくれて。飲みましょうよという話になって、連れてきてくれたのが沖田くんだったかなと記憶してます。おそらく、その頃はベリトランス時代の最後のほうでしたかね。
沖田:そうですね。ベリトランスの非常勤の役員期間が残っていて、1年ぐらいプラプラしていいよみたいな状態だったので、とりあえずいろんな人に会おうという感じで。
自らの人生を問い直し、SBI Ripple Asia(SBIとRippleのJVであるブロックチェーン企業)に参画
手嶋:ベリトランスを離れて、たくさんの選択肢があった中でSBIグループ、北尾さんのところに一旦戻って。その中で投資額も大きいであろう最先端のブロックチェーン事業を手がけるSBI Ripple Asiaの社長を務めることになります。アメリカのフィンテックベンチャーのRipple社とSBIホールディングスのジョイントベンチャーですね。これはどんな流れで、かつどんなことをやっていたんでしょうか?
沖田:ベリトランスを離れてプラプラしてるときに、アメリカに2〜3週間行ってたんですよ。そのときに参加したカンファレンスに、クリス・ラーセンというRippleの共同創業者が登壇していて。10年以上前に、東京で北尾さんに紹介していただいたことがあって、良いきっかけだと思ってクリスと話をしていたんですよ。当時はまだSBIの出資やジョイントベンチャーの話はなくて、僕としては「話したら面白そう」くらいの感じでしたし、本当は自分で起業しようかなとも思っていたんですが、ご縁で社長を務めることになった感じですね。
クリスは非常にフランクだし、年齢は結構上でもう60歳ぐらいですけどテクノロジーにも明るくて。一方で、勝負どころの迫力や凄みも持ち合わせていて。一緒に仕事するという意味では、ユニークな人でしたね。
手嶋:解説しておくと、SBI Ripple Asia自体は海外送金を滑らかにするような思想を持っている会社。同社が提供するプラットフォームで使われている仮想通貨がリップルです。SBI Ripple Asiaは、日本国内外の金融機関と接続して、ブロックチェーンでいかに送金コストを下げていくかみたいなトライをしていましたよね。
国内外のフィンテック産業の変化について情報が入ってくる立場にあったと思うんですけど、当時はどんなことを手がけながら、今後の流れをどのような大局観で見ていたのかをお話ししてもらえますか?SBI Ripple Asiaを退任してからナッジ設立前の時点で考えた一連の流れでもいいですし。
沖田:ベリトランス時代に金融審議会の専門委員をさせていただいていた頃からずっと同じことを言っているんですけど、インターネットのインダストリーって長いじゃないですか。インターネットの特徴や本質っていろいろありますけど、やっぱり一番大きいのは民主化の促進。私はよく「パワーシフト」という言葉を使っています。インターネットが、小売も広告もメディアもVC業界もあらゆる産業を変えてきたじゃないですか。今も変化の最中だと思いますが。
それに比べて、金融はあまり変わっていない。ただ今後、インターネットの荒波、パワーシフトの波は金融にも必ずやってきますよねと。ちなみにSBI Ripple Asiaのときも国際送金を扱っていましたが、日本では国内送金もやっていたので、ほとんどの国内銀行さんは取引先なんですよ。
手嶋:そうか。今まさに起きてる銀行間送金の決済手数料を下げる試みを、ブロックチェーンを活用して国内でもトライしてたって感じでしたね、当時は。
沖田:そうです。ですので、今でこそ全銀ネットの委員とかやってますけど、当時は全銀ネットをぶっ壊すぞ、みたいな(笑)。
手嶋:そういうのがあったからこそ全銀ネットも動いて、いよいよ重い壁が開いたっていうのはあるでしょうね。
沖田:ですね。全銀行の8割ぐらいが参加してくれたときに「今のままでいいなんて、誰も思っていない」「でも誰1人として声を上げてこなかった」と。空気を読むといえば良い表現かもしれないですけど。その点、私はもともと銀行業界は門外漢ですから、「これっておかしいんじゃないのか」と思ったことを自然体で話していたら、中の人たちから「ずっと言えなかったことを言ってくれた」と思ってくれたようで。
みんな、もうテクノロジーやDXの時代が来るのはわかっていて。そこで私からは「世界中でチャレンジャーバンクが起きてきてますよ」とか、キャッシュレスの話をいろいろとしていたんです。わかってはいるけど認められずに、自分たちにとって不都合な真実に蓋をしてしまうところがあって、なかなか変わらない。いくら外圧をかけても、やっぱり本人たちが納得して変わるまでには少し時間がかかるなと思いましたね。
手嶋:SBI Ripple Asiaを退任したのはいつでしたっけ。
沖田:2019年かな。
手嶋:世界のフィンテック業界を見ると、2017〜2018年頃に立ち上がった会社が結構多いですよね。その頃にはもうフィンテックスタートアップは世界を席巻していた感じですか。
沖田:そうですね。なので、日本も遅ければ、私も遅いんですよ。もはやフィンテックが死語になりつつある時期でした。これまでの人生はインターネットにしろeコマースにしろアジア市場への進出にしろ、人より一歩前に始めているんですよね。
基本的な考え方としては、大きな波がやってくるときに遅いより早いほうがいいと。半歩遅れたらもう致命的じゃないですか。だから半歩早いのがベストだけど、半歩前にドンピシャには行けないんで、それであれば一歩前二歩前に先にいて、波がやってくるまでじっと耐えて待ってるほうが絶対いいだろうと。
ただ、SBI Ripple Asiaを退任したのが2019年、ナッジを設立したのが2020年。フィンテックの波はもうバシャバシャ来ちゃってて、今から遅れて参加するって、ちょっと遅すぎるなっていうのは、その時思った本音ですね。
前半はここまでです。後半は、そんな沖田氏が設立した「ナッジ」の挑戦について伺っていますので是非ご覧ください。